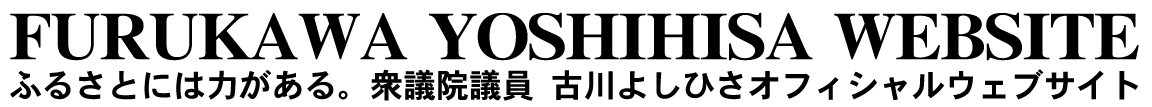2024.7.26 政党政治をオーバーホールする ~ 令和の政治改革へ ~
2024.7.26 令和の政治改革
2024.7.22 自民党はモデルチェンジできるか
2024.7.19 日本政治の抜本改革
2023.9.16 私の西郷隆盛観〜西郷南洲東京顕彰会にて講演
こちらのコラムは別ページが開きます。
2023.8.16 台湾について(その1)~戦争回避~
2023.8.16 台湾について(その2)~日中共同声明~
2023.8.16 台湾について(その3)~総統選挙~
2023.5.11 今こそ、石橋湛山
2023.2.1 外国人との共生(その1)~共生の基本法を~
2023.2.1 外国人との共生(その2)~技能実習~
2023.2.1 外国人との共生(その3)~特定技能~
2023.2.1 外国人との共生(その4)~難民、避難民~
2023.1.20 マーケットは見ている
2023.1.3 米国と中国、双方にはたらきかける
2023.1.2 馬を制御できるか
2022.12.27 輸入が止まったら?(その1)~食料危機~
2022.12.27 輸入が止まったら?(その2)~エネルギー危機~
2022.12.26 防衛は誰が負担する?
2022.11.21 マーケットの警鐘が聞こえるか
2022.11.16 防衛の試金石
2022.10.31 「防衛力」「抑止力」と「外交力」
2022.10.14 新しい国際秩序へ
2022.6.6 日中国交50年に思うこと
2022.6.6 王道を語る
2022.5.16 「世界の平和と繁栄への貢献」(中曽根国連演説)を読む(その1)
2022.5.16 「世界の平和と繁栄への貢献」(中曽根国連演説)を読む(その2)
2022.5.16 「世界の平和と繁栄への貢献」(中曽根国連演説)を読む(その3)
2022.3.22 歴史の本流
2022.3.21 国際社会の連帯を
2021.8.10 核兵器のない世界
2021.6.22 コロナ検証委員会を設置すべし
2021.6.18 朝のNHKニュース
2021.6.16 経済安全保障の議論に思う
2021.6.15 武道という生き方(その1)~危機に備える~
2021.6.15 武道という生き方(その2)~抜かない、抜かせない~
2021.6.15 武道という生き方(その3)~精神的高みに立つ~
2021.6.10 「財政民主主義」と独立財政機関
2021.4.8 中国にどう向き合うか(その1)~孫文の大アジア主義演説~
2021.4.8 中国にどう向き合うか(その2)~中国の覇権主義~
2021.4.8 中国にどう向き合うか(その3)~米中対立と日本~
2021.4.8 中国にどう向き合うか(その4)~「平和五原則」の再確認~
2021.4.8 中国にどう向き合うか(その5)~日本の志~
2021.2.22 “アメリカ・イズ・バック”
2021.2.18 東京オリンピック・パラリンピック
2021.2.15 大深度地熱発電
2021.2.8 分散自立国家論 ~昔から分散自立だった~
2021.2.8 分散自立国家論 ~法律、税制、ファイナンス~
2021.2.3 ファイブ・アイズ
2021.1.30 ワクチン。ワクチン。ワクチン。
2020.12.18 地球温暖化と食料 ~ サツマイモ基腐病 ~
2020.11.25 「気候非常事態宣言」、採択さる
2020.10.28 気候危機に、立ち向かう。
2020.10.20 日本と韓国、共通の志
2020.10.16 新しい「列島改造論」
2020.10.12 続・日本の食料は?
2020.10.8 「戦戦競競」
2020.8.17 「米中冷戦」にあらず
2020.8.12 核兵器禁止条約に署名すべし
2020.8.11 「敵基地攻撃能力」の愚
2020.7.22 日本はどう生きるか(その1)~拠って立つところ~
2020.7.22 日本はどう生きるか(その2)~対米追従か~
2020.7.22 日本はどう生きるか(その3)~対中連携か~
2020.7.22 日本はどう生きるか(その4)~自立路線~
2020.7.22 日本はどう生きるか(その5)~政治はどうあるべきか~
2020.7.2 自ら変革するとき ~脱炭素~
2020.6.24 主権国家としての危うさ
2020.6.22 「自由」を奪う中国を非難する
2020.5.8 新型コロナ、自由と民主主義
2020.4.27 日本の食料は?
2020.4.20 大掛かりな失業対策の必要
2020.4.16 今こそ、イランの声に応えよ
2020.4.12 アタマを有事モードにきりかえよ
2020.3.25 “有事”の医療体制を整えよ
2020.3.12 “乾坤一擲”の財政出動
2020.2.22 これからの日米関係 (その1)~未来を展望するとき~
2020.2.22 これからの日米関係 (その2)~日米安保条約~
2020.2.22 これからの日米関係 (その3)~海上自衛隊派遣~
2020.2.22 これからの日米関係 (その4)~歴史の教訓~
2020.2.22 これからの日米関係 (その5)~提言~
2020.2.12 86万4千人
2020.2.1 国の独立
2020.1.24 財政規律はどこへ行った
2020.1.22 “一国二制度による統一”の行方
2020.1.14 国を誤ることなかれ
2020.1.5 「日米同盟」と言うならば、米国を諌めよ
2019.12.27 日本の「国是」が変更せられた日
2019.12.19 気候クライシスにどう向き合うか
2019.12.10 アベノミクスは”時間切れ”
2019.12.5 中村哲氏に哀悼の誠を捧ぐ
2019.11.25 香港と、民主政と、日本と
2019.11.11 地位協定を改める責任
2019.11.6 首里城が象徴するもの
2019.10.28 北東アジアに集団安全保障メカニズムを
2019.10.20 海自艦派遣に反対する
2019.10.16 防災の体制づくりが急務
2019.10.8 消費税、増税に思う
2019.9.26 何のための憲法改正か
2019.8.24 断じて、「有志連合」に参加してはならぬ
政党政治をオーバーホールする ~ 令和の政治改革へ ~
2024.7.26
どんな政策であれ、国民に受け入れられなければ結局はうまくいかない。民主政治は世論なのだ。大事なポイントは二つあると考えている。(1)国民から信頼されること。(2)民意の反映された政権をつくること。この二点だ。
「裏金問題」で信頼は根こそぎ失われ、民主政治の背骨が折れた。だが「裏金問題」の以前から、いまの政党政治の限界は明らかだったように思う。異常なまでの“投票率の低さ”が一例だ。国民はあきらめ(シラケ)ているということだし、政権は一部の国民の支持でしか支えられていないということだ(私自身、忸怩たる思いです)。
これからさき日本は、国の方針や政策を大胆に転換し、果敢に実行していかなければならない。しかし、国民の支持が脆弱な政治態勢のままで、日本丸の舵をしっかり取っていけるものだろうか。
私はこの機会に政党政治をオーバーホールしたい。しかも混乱を最小に抑え、できるだけ短期間のうちに済ませたいと考えている。
そこで「令和の政治改革」を提案したい。「政治資金の透明化」「国会改革」「選挙制度改革」をパッケージにして国民の前で約束し、一つ一つ実行していくのだ。来年の通常国会が終わるまでに(およそ1年だ)基本的な法整備を仕上げるくらいのスケジュール感でやる。そうすれば、ちょうどひと区切りついた頃に参議院の通常選挙、秋には衆議院議員の任期を迎える。ここで国民の審判を仰ぐのだ。
30年前の「平成の政治改革」では5~6年を費やした。しかし今の日本にその余裕はない。「令和の政治改革」は1年で済ませたい。
令和の政治改革
2024.7.26
~政治資金の透明化~
なぜ政治資金が優遇を受けられるのか? と言えば、民主主義を支えるコストとみなされるから、だろう。ならばキチンと政治活動に使ったと説明できなければならない。説明できないのなら優遇は受けられない。当たり前のことだ。
この当たり前のことが行われない。“政治家は自分たちだけズルしている”“ルール破っても平気な顔”“政治家はまだペナルティ受けてない”…国民の眼にはこう映っている。
そんな政治が信頼されるはずがない。“政治家は怪しいカネにまみれている”と思われている間は、政治に信頼は得られない。したがって「政策活動費」も「旧文書交通費」も説明できることを原則に透明化しなければならない。
~国会改革~
“与野党は足の引っ張り合いばかり!”と感じる方は多いと思う。それはそれで事実ではあるが、(私が言うのもナンだが)案外と国会審議はしっかり行われているのであって、足の引っ張り合いにしか見えないことは残念であり国にとっても不幸である。そこで、たとえば「与党による事前審査」を廃止して、与野党いっしょに法案審議してはどうか…? その他、国会のルールや慣例を見直す必要性を感じている。
また、首相が百数十日も国会に縛られる…、閣僚が国会日程のため国際会議に出席できない…、今の時代こんな慣行は改めるべきだろう。国会答弁は主に副大臣の担当とすべきだ。
それから、官庁職員が膨大な国会対応事務で忙殺される実態を、急ぎ、改めなければならない。不毛な作業を官僚諸君に強いる場面が多いのは事実だ。実状はすでに限度を超えている。
~選挙制度改革~
衆議院「小選挙区比例代表並立制」を「中選挙区連記制」に改めるべきだ。選挙制度はどれも一長一短だが、今もっとも優先されるべきは“民意の反映”だと考えるがゆえに、私は「中選挙区連記制」を強く推す。「連記制」は複数の候補者に投票できることから死票が減り、民意がより反映されたとの実感を得やすい。
民意をもっとも反映できる制度、つまり「中選挙区連記制」のもとで総選挙が実施されたとして、選挙結果をうけて樹立された政権は、国民の最大支持を得られた政権である。ならばこの政権は、最大民意を推進力として、果敢に政策を実行できるのではないか。要するに「中選挙区連記制」によって、時代の転換期にふさわしい政治体制をつくれるのではないか。
「小選挙区制」はただ一人を選ぶものである以上、“対決”を呼び込む。A候補とB候補あるいはA党とB党、どうしても対決して白黒つけなければならない。それが「小選挙区」だろう。しかし、これからさき巨大地震が起きたとか、円の底が抜けたとか…の国難が日本を襲ったとき、協力して事にあたれる国会でありたい。国家的危機に対応できる政治であるために、今のタイミングで、対決原理の「小選挙区制」をやめておきたいと思うのである。
自民党はモデルチェンジできるか
2024.7.22
昭和生まれの世代なら、『巨人、大鵬、玉子焼き』に聞き覚えのある方も多いだろう。かつての高度成長期の、多くの国民の好物であり、強さや豊かさの象徴でもあった。当時の価値観、世相や雰囲気をうまく表わしていると思う。
ここに『自民党』を付け加えてもいい。右肩上がりの時代、政治はまさに“自民党モデル”でうまく機能したからだ。たとえば政官財連携や、護送船団方式。それぞれ負の側面があったにせよ、当時これらのフォーメーションがフル回転することで日本経済がグングン伸びたのは事実だ。
しかし昭和は平成をへて令和となり、「右肩上がりの時代」は「縮小・成熟の時代」へと移行した。なにより、私たち日本人の価値観がずいぶんと多様化した。家族のあり方から、働き方、社会のあり方まで、あらゆるものが変化した。世界を見回してもグローバル化の流れは凄まじく、国際秩序だって日々激動している。時代はすっかり変わったのだ。
なので、時代の変化に合わせて、制度や政策、発想や仕事の仕方を変えていかなければならない。たとえば社会保障がそうだ。昭和に設計された制度が今必ずしも国民の安心につながっていない。ならば政治は、国民との対話を通じて、新しい時代の社会保障のあり方を示すべきなのだ。
時代が激動しているのに自民党は変わらない。旧来の“自民党モデル”からいまだ抜け出せないままだ。今回の派閥の不祥事だって“自民党モデル”の名残だと言える。「政治とカネ」もしかり、「派閥」もしかり、「政策決定プロセス」もしかり。かつての成功体験を引きずり、胡坐をかいたままの自民党…という側面がたしかにある。
自民党は、モデルチェンジしなければならない。「党と議員との関係」、「党と党員との関係」、「党内ガバナンスのあり方」、「政策決定のあり方」…これらを総点検して、改めるべきことは思い切って改める。こうして、果敢に自己改革する姿を国民のみなさんに見てもらうのだ。
誰かが自民党を建て直してくれるわけじゃない。自分が自民党を根っこから建て直す! そんな仲間が何人いるか。自民党はここにかかっていると思う。
日本政治の抜本改革
2024.7.19
いわゆる裏金問題で自民党への信頼は地に墜ちた。国民のみなさんからすれば、物価が上がって大変だ…生活だって楽じゃない、それでもキチンと税金を納めて真面目にがんばっている…。それなのに政治家は自分たちにはお手盛りでズルイことをやっている。ルールを破って平気でいる。こんな政治家たちの言うことを一体誰が素直に聴けるか?! ということだ。一番大切な「信頼」が失われ、民主政治の背骨が折れた。
さらに深刻なのは、問題表面化後の自民党の迷走ぶりだ。自民党に国を任せて大丈夫なのか…? 国民の不信不満はそこまで来ていると実感している。昭和30年の保守合同以来、国民政党を自認しながら政治を主導してきた自民党だが、今日、これほどまでに信頼を失ってしまった。
われわれ自民党は、不退転の覚悟をもって自己改革に取り組まねばならない。そしてその姿を国民のみなさんに見ていただかなければならない。まず何よりも、これが出直しの第一歩だ。
しかし、それは当然のこと。自民党が自ら襟を正し、自己改革に取り組むのは当たり前のことにすぎない。国民の政治不信の根底には、根本的な改革を断行できない、劣化した政治に対する苛立ちと腹立たしさがあると思う。自民党はここを直視して、為すべき事を為さなければならない。
今月4日、岸田自民党総裁あてに「日本政治の抜本改革」を申し入れた。
「日本政治の抜本改革」断行へ向けての申し入れ
前文(省略)
1.第三者機関の設立や「文通費」公開ルールの策定など、政治資金規正法改正の残された課題に取り組み、早期に結論を得ること。
2.選挙制度改革について、党内に議論の場を設けると同時に、衆議院議長のもとに正式に各党協議会を立ち上げ、議論を進めること。
3.閉会中も憲法審査会を開催し、改正条文案の策定へ向けての議論を進めること。
4.省庁再々編をはじめとする行政改革、国会改革についても党内において議論を開始すること。
台湾について(その1)~戦争回避~
2023.8.16
米ソ冷戦の時代、両国は対立していても直接対決することはなかった(核戦争になるから)。それを考えれば、この先、米中が直接砲火を交えることも基本的にはないと思う。
もし仮に、米中が衝突するとすれば、そのとき、矢面に立たされるのは日本だ。戦火に焼かれるのは日本であり、最悪の場合、わたしたちは国を失う。したがって、戦争回避は日本の“生命線”である。そのための外交に全力をあげることが、日本生き残りの唯一の戦略だ。
考えられる火ダネの一つは“台湾”である。いわゆる台湾有事などという事態に至らぬよう、米中台には、それぞれの真意を正確に把握し合う努力が必要だ。日本はその後押しに心を砕くべきである。
台湾について(その2)~日中共同声明~
2023.8.16
1972年、日本側=田中角栄総理・大平正芳外相、中国側=毛沢東国家主席・周恩来首相のもとで国交回復が実現した。その際の「日中共同声明第三項」には、台湾をめぐる考え方の原則が織り込まれている。そのこころを言うならば、“平和的話し合いで一つになるのなら受け入れますよ”ということだろう。
したがって日本は、日中共同声明にしっかりと軸足をおき、中国に対しては“力づくじゃダメですよ”と言わねばならないし、米国に対しても“煽っちゃダメですよ”と言うべきだろう。
実際、米中は激しく対立しながらも、この点については微妙に気を遣い、ともに慎重にやっているように見える。
しっかりすべきは日本である。いわゆる台湾有事をめぐる勇ましい言説があるが、とくに日本の政治家は慎重であるべきだ。日本外交は、原則を重んじ、戦争回避をもって大義とすべきである。
台湾について(その3)~総統選挙~
2023.8.16
台湾では、来年1月に総統選挙が予定されており、その行方次第では諸情勢にも影響がありうる。
だが、大事なのは台湾の国民自身の意思である。彼の国民は(当然ながら)豊かさや平和を求めているのであって、中台関係の“統一か独立か”といった極端な展開を望んでいるとは思われない。
日本も、米国も、もちろん中国も、台湾の選挙にくちばしをはさむべきではない。誤解を招くような言動にも気をつけるべきだ。まちがっても、対立や衝突の火の粉を吹き込むようなことをしてはいけない。
今こそ、石橋湛山
2023.5.11
石橋湛山は、思想家であり、言論人であり、政治家である。かつて日本が、国をあげてこぞって帝国主義になだれを打つ、まさにそのとき、湛山は単騎真っ向から反対をしている。
そればかりではない。湛山はかならず、日本の進むべき道はこうだと具体案を示しているが、そのスケールが壮大なのだ。『一切を棄つるの覚悟』や『大日本主義の幻想』などの論考を読むと、今なお圧倒される。
湛山から何を学ぶか。
第一に、構想力。湛山は、目先の損得を超えて、歴史の大きな流れを見据えていた。
米中の激しい覇権争いのなかで、「日本がどうやって生き延びるか」という大命題について、そのヒントを湛山の構想力に学びたい。「日米同盟で中国を封じ込める」という単純な発想だけでは、国を失うことになりかねないから。
第二に、自立心の大切さについて。湛山は一貫して、自立心こそが自由と民主主義、国際平和の基礎だと説いている。
だが今日、わたしたちの社会は自立しているだろうか。わたしたち政治家や国民に自立心はあるだろうか。たとえば、社会保障や安全保障のコストについて“誰かが負担してくれる”と他人まかせになってはいないだろうか。
第三に、覚悟である。たとえば、すでに日本の敗北が見えていた昭和19年。湛山は、軍部の監視をかいくぐり、政府内に「戦時経済特別調査室」を設置させている。遠くない敗戦を見すえて、ひそかに戦後に備えようとしたのだ。われ一身に背負わんの気概、まさに鬼気迫るものがある。
逃げない。見て見ぬふりをしない。そして危機を自らの責任として引き受ける覚悟。今、わたしたち政治家に、その覚悟はあるだろうか。
激動の時代、湛山スケールの構想力、自立心そして覚悟が必要だ。
外国人との共生(その1)~共生の基本法を~
2023.2.1
ある歴史家が言った。何処へ行けばよいかを知るために、何処から来たかを知らねばならない。だから歴史を学ぶのだ、と。名言である。
日本人は何処から来たのだろうか?
私たちのご先祖は、南方から、大陸から、半島から、北方から、その折々に海を渡って来た。これ以上先に行けないので(太平洋だ)、この島々で折り合いをつけながら生きねばならなかった。こうした多文化共生のプロセスがあったからこそ“和をもって尊し”の日本文化ができあがったのだろう。
では、日本人は何処へ行くのか?
それは決まっている。生来、多様性をみとめる日本民族なのだから、これからも世界(なかんずくアジア)の人々と共に生きていく。お互いを認め、尊重し、助け合いながら、おおらかに生きていくのだ。日本人だけで小さくまとまって生きる…なんてことはできない。世界のなかの日本なのだから。外国人を交えてどんな社会をつくるのか、あらためて国民みんなで考えよう。
ところで、在日コリアンやインドシナ難民、日系人との過去をふりかえれば分かるとおり、これまでの日本社会は必ずしも良き共生社会だったわけではない。政府にしても長期的展望に立った構想や具体策を持ってはいなかった。
でもだからこそ、法務省・出入国在留管理庁に白羽の矢があたった。日本にもようやく共生政策の司令塔が出来たのだ(2018年)。
この司令塔を、素晴らしいものに創りあげよう。
心理学・文化人類学・地政学・国際法などの専門知識はもとより、人権感覚や歴史観・文明観をあわせもった司令塔に創りあげるのだ。そうすれば、世界の大海原で、日本民族の進路をしっかりと見定める水先案内役になることだろう。
だから基本法が欲しい。共生の理念・哲学を謳いあげ、ふさわしい体制や機能を規定するのだ。立派な仏像が彫れたのである。つぎは魂を入れるのだ。
外国人との共生(その2)~技能実習~
2023.2.1
改めるべきは改める。当然のことのようだが口で言うほど簡単ではない。なぜなら、それは時として自己否定となり先輩の批判ともなるからだ。わたしたち日本人には辛いことである。
それでも率直に「よし、改めよう!」と決心できるならば、その誠実さと勇気をもてるならば、もう怖いものはない。
技能実習制度も始まって三十年、改めるべきを改める場面に来ていると思う。外国人への技術供与・国際貢献を本旨とする制度だが、実際には労働力確保に利用されることが多かった。この「ホンネ」と「タテマエ」のギャップが様々な問題を生んできたと言える。これを改めよう。
日本に来るのは労働力という商品ではない。私たちと同じ生身の人間だ。大切な人生の一時期を日本で生きる彼ら彼女らに“日本に来て良かった”と思ってほしいし、同じく受入れ側にも“来てもらって良かった”と思ってほしい。そうなって初めて制度は持続的なものとなる。
改めるとすれば、たとえば労働者としての権利を明確にするとか、あるいは特定技能との関係性を整理して先々を見通せる制度に再設計する、など幾つか論点があるだろう。
昨秋から政府も専門家を集めて集中的に議論を始めている。期待をもって見守りたい。
いま、全国で人手不足が深刻だ。でもだからといって“安い外国人で”という発想は通用しない。それは生産性向上とカイゼンによって乗り越えるべきなのであって、“安い外国人”だのみではもはや事業継続は難しい。もしもまだ、そんな発想が残っているなら訣別すべきだろう。
制度であれ、意識であれ、改めるべきは改める。わたしたちはその誠実さと勇気を発揮すべきときを迎えている。
考えてみれば、わたしたち日本も多くの文物や技術を諸外国に学んでやって来たし、その日本も普段から(特段の意識なく)外国人への技術供与・国際貢献をしているように思う。日本は知らず知らずに恩返しをし、世界の発展に貢献しているのかもしれない。
技能実習の「ホンネ」と「タテマエ」の使い分けをやめて、制度を根底から考え直すことは、わたしたち自身をも見つめ直す良い機会である。
外国人との共生(その3)~特定技能~
2023.2.1
映画『ファミリア』を観た。クリント・イーストウッドの『グラン・トリノ』を上回る内容(*個人の感想です)に強い刺激を受けた。日系ブラジル人の過酷な現実に、言いようのない日本社会の不条理を思う。
かつて景気の良い時代、産業界は多くの外国人労働力(たとえば日系ブラジル人)を求めたが、不景気になると一転して彼ら彼女らを放り出した。結果として国家や国境の谷間に転落してしまった人々のあることを、わたしたちは知るべきである。
2018年、わが国ははじめて外国人労働者の受け入れに道を開いた(特定技能)。各業界と各所管省庁とで欲しい人数を割り出し、その受入枠のなかで技能労働者を認めていく制度だ。
コロナの影響もあり新制度はまだ充分に定着していない。が遠からず、制度がうまく機能しているかを検証し必要ならば見直すことになる。
外国人労働者受け入れにあたっては、その人数設定を産業界まかせにしてはならない。かつての苦い経験を繰り返してはいけないから。
そればかりではない。それぞれの地域社会には受入れ能力・キャパシティがある。言葉も生活習慣も異なる外国人を受け入れるには、おのずと適数があるはずだ。ドシドシ入れれば良いということではない。
そしてその適数の判断は、国家主権の発動として、法務省・出入国在留管理庁において一元的に為されるべきである。
外国人をただ労働力とみなしていては共生社会は築けない。ともに社会を構成する者として、その言語や文化習俗・宗教などへの理解や協調が欠かせない。これらの違いや多様性を前提に、寛容な心映えをもって共生政策を組みあげていく必要がある。
法務省・出入国在留管理庁にはその能力を十分に身につけて欲しい。日本の未来を見すえながら、“司令塔”の役割を全うしていって欲しい。
外国人との共生(その4)~難民、避難民~
2023.2.1
“情は他人のためならず”、“困ったときは相身互い”…。日本には良い言葉がたくさんある。ウクライナ避難民の受入れ支援にあたって、全国からたくさんの支援の申し出があった。すばらしいことだと思う。
わが国は「難民鎖国」と揶揄されて久しい。とくに、ウクライナ避難民に素早く対応したことと比べられてか、“日本はアジア人に冷たい”とことさらに言われた。でも、それは少し違うと思っている。
たとえばミャンマー。2021年のクーデターで帰国できぬ者が続出したが、日本政府は数十名の難民認定のほか数千名規模で在留特別許可を出してきている。
アフガニスタンもそうだ。カブール陥落にあたって大使館関係者など数百名が退避したが、その後も、日本政府は事情を酌んで約百名を難民認定した。しかも個別審査を省略し、百名をまとめて柔軟に認定している。
新制度も準備中だ。今国会提出の入管法改正案には「補完的保護対象者認定制度」創設が盛り込まれている。これは、たとえ難民条約上の「難民」に該当しない場合でも“真に庇護を必要とする外国人”ならば保護できるようにする、そのための法整備である。
2018年に産声をあげた出入国在留管理庁は、すでにこうして動き始めている。みずから成長しつつあるのだ。
これからも国をあげて法整備や、体制づくり、人づくりに力を注ぎ、また国民の理解と協力を得ながら、立派な出入国在留管理庁に育ってほしい。心からそう願う。
世界は激動し、時代は変わる。これからの時代、わたしたちの社会が“真に庇護を必要とする外国人”とどう向き合っていけるか。それは出入国在留管理庁の立派な成長にかかっている。そして同時に、わたしたち日本民族の度量と気高さとにかかっていると思う。
マーケットは見ている
2023.1.20
減税(7兆円規模)をかかげた英国のトラス政権だったが、マーケットが反応し、金利が上がり、年金資金が心もとなくなって、あっという間に退陣に追い込まれた。つい数か月前のことだ。
たとえ国民が支持しても、マーケットの信認が得られなければ政策は実行できない。それどころか政権だって倒れうる。為政者はマーケットに見られていることを片時も忘れてはいけない。
世界で、最もマーケットの目を意識すべきは日本である。財政、金融政策とも日本ほど状況の悪い国はないからだ。トラス退陣劇に背筋を凍らせたのは私だけではないはずだ。
これまで徐々に格付けを下げられてきた日本国債がこのさきマーケットにどう評価されるか。これは極めて重大な意味をもつ。
さて、自民党では防衛費の財源をめぐって議論がつづいている。もちろん議論することは大事である。しかしその中身に、私は不安を禁じ得ない。これだけ状況の悪い日本国において、しかも政権与党たる自民党が、こんなに自由奔放にふるまっていて大丈夫なのか。「国債を発行せよ」「国債償還ルールを見直せ」などの議論は不用意に過ぎる。
マーケットの目を誤魔化すことはできない。ましてや小手先のレトリックなど通用しない。マーケットは見ている。もはや、見られている自覚のない議論は危険である。
わたしたち政治家がいま最優先に考えるべきは「財政規律」だ。口先だけの「財政規律」ではない。行動をともなった「財政規律」である。「財政規律」を死守する姿勢を行動で示す、それ以外にない。マーケットは見ているのだ。
米国と中国、双方にはたらきかける
2023.1.3
防衛力整備は独立国家として当然ではあるが、勢いまかせではいけない。中国の脅威と中露朝連携の不穏があるにせよ、防衛力・抑止力ばかりにのめり込むのは危ういことだ。
最近の防衛力強化の大合唱や一直線にミサイル配備を求める声に、なにか前のめりの危うさを感じてしまうのは私だけか。
いま、日中の間には、(尖閣諸島をめぐる対立はあるにせよ)全面戦争をするだけの理由は存在しない。東アジアに火ダネがあるとすれば、台湾をめぐって米中対立が衝突に発展する場合であろう。
仮に戦争となる時は、かなりの確度で日本は巻き込まれる。いや、日本列島こそが戦場となるだろう。
第二次世界大戦後、共産勢力の拡大膨張が現実的な脅威となった時代。米国のダレス国務長官は日本に対し、再三にわたって再軍備を要求する。だが当時の吉田茂総理大臣がそれをのらりくらりとかわそうとした話は有名である。
もしもあのとき、吉田がダレスの求めに積極的に応じていたら、日本軍将兵は間違いなく朝鮮戦争の最前線に送られ“やりぶすま”にされただろう。いま日本がおかれた状況も大きくは変わらない。もしここに吉田茂がいれば、「日米同盟で中国に対抗せよ」という話にかんたんに乗るはずがない。
どんなことがあっても日本を“やりぶすま”にしたくない。今日、私たちがまず第一に考えるべきは、これではないのか。
戦争回避こそ唯一の戦略。米国に対しても、中国に対しても、あらゆる情理をつくし外交技術を駆使して衝突の芽を摘む。これに全力をあげることこそ日本生き残りの道である。
馬を制御できるか
2023.1.2
一国の財政は、多頭立ての馬車に似ている。馬の中には暴れ馬もいるが、これらを上手に束ねられるか。目的地まで無事たどり着けるか。それはひとえに御者の腕にかかっている。言うまでもないが、御者とは財務大臣であり内閣総理大臣である。政治指導者という言い方をしてもよい。
御者がしめたりゆるめたりの手綱さばきをしくじると、馬車は暴走し、下手をすれば転覆する。つまり、財政運営次第では国が潰れ、国民が塗炭の苦しみを味わうことにもなる。
高橋是清大蔵大臣(日銀総裁・首相)は名御者だったと思う。状況に応じて、ある時は手綱をゆるめ、ある時は手綱をしめる。高橋は、その臨機応変の機動性・柔軟性こそ財政運営の要諦だと考えていたのだと思う。
昭和11年、高橋は膨張する「軍事費」の削減を強く主張した。暴れ馬の手綱を引こうとしたのだ。だが軍部の反感を買い、高橋は青年将校の凶弾に斃れることとなる(2・26事件)。こうして暴力によって名御者を失った馬車がその後どうなったか。歴史はハッキリと答を出している。
いま、制御が難しいのは、何と言っても「社会保障関係費」だ。令和5年度予算案では一般会計歳出のなんと3分の1を占めて毎年増大の一途である。だが、何よりも心配なのは「国債費」だ。今は歳出の4分の1ほどだが、金利が上がれば必然的に雪ダルマ式に膨れあがる。
考えるだけでも恐ろしい暴れ馬。これをどうやって制御するか。その手立てすら見いだせない。
わが国の財政は、もはや、財務大臣や総理大臣の力量に頼っていて済む段階にはない。まずは国会議員全員(与野党問わず)が目の前の深刻な現実を直視することだ。見て見ぬふりをせず、現実に向き合うところから始めなければならない。
輸入が止まったら?(その1)~食料危機~
2022.12.27
ロシアのウクライナ侵攻によって、世界は一気に「食料危機」「エネルギー危機」に直面した。では、もし、台湾で何かが起きたらどうなるか。
そのときはまず台湾は封鎖され、バシー海峡も封鎖されるのだろう。輸入の99.5%を海上輸送に頼る日本が、「食料危機」「エネルギー危機」に陥るのは火を見るより明らかだ。
私は最近、あまり食料自給率というコトバを使わないようにしている。なぜなら、もし輸入が止まったら食料自給“率”は自動的に100%、国民が飢えていても100%である。数字は相対的なもので状況次第で変化する。なので“率”の数字を語ることにはあまり意味がない。
大事なのは食料自給“力”だろう。いざ輸入が止まっても、国民が必要とするカロリーと栄養素を生産、調達できるだけの“力”。これが必要だ。
終戦当時、日本国民は飢えて餓死者もでた。当時の人口は7200万人、農地は600万ヘクタール、米の生産は900万トンだった。では現在はどうかというと、当時に比べて人口は1.7倍に増え、農地は3割減り、米生産は4分の1減った。つまり日本は、餓死者をだした終戦時よりも食料自給力を格段に落としている。輸入がストップすれば小麦、大豆が入らないのみならず、石油はじめ肥料などの諸資材も全部止まる。日本は確実に飢える。
ところで、スイスの農業は日本とよく似ている。山地が多くて平野が狭く、農家一戸あたりの平均耕作面積も日本と同じくらい。輸入に頼らざるをえないところも似ている。
5年前、スイスは憲法に「食料安全保障」条項を追加し、農業政策を大転換した。農家の所得支持を目的とする「直接支払」から、農地を保全し生産力を維持する「供給保障支払」へ、と政策の重点を大胆に転換したのだ。あきらかに、食料自給“力”に着眼した政策転換である。
日本も食料自給力を考えるときが来た。
輸入が止まったら?(その2)~エネルギー危機~
2022.12.27
エネルギーについても同様のことが言える。輸入に頼りきった国の構造そのものを改めなければならない。
これまで無資源国と言われてきた日本だが、実は、再生可能エネルギーのポテンシャルはけっこう、いや相当に高い。たとえば地熱発電においてはアメリカ、インドネシアにつづいて世界第3位の包蔵量をもっている(日本は火山国だ)。もっとスゴイのは洋上風力で、陸に近い処では漁業の関係があって難しいけれど、もう少し沖合での浮体式を含めて考えると海洋国家日本のポテンシャルは相当のものだ。
今回の物価高騰対策で、政府はガソリン、電気、ガスの価格を抑えるため巨額の資金を投入している。10兆円になんなんとする莫大な金額だ。けれども、もったいない。その資金を省エネや新エネルギー開発・普及に投じるならば、相当なことができるはずだ。エネルギーの自給体制を強化するために使うべきだったと思う。
再生可能エネルギーのポテンシャルは莫大なのだが、それらをすべて財政の力で具現化するのは無理だ。何か良い方法はないだろうか。滔々と水をたたえる大池の、堤の何処を切ってやれば水はうまく流れていくのか。これを考えぬくことだ。
ヒントはデンマークにあった。デンマークでは、風力発電所を建設する際に少なくとも15%は地元資本を入れる、そう法律で決まっている。ということは、少なくとも風力発電所が生み出す富の15%分は地元に還元される、ということだ。
日本でも地熱発電所や風力発電所をつくる際に、たとえば3割は地元資本を使うようにしたい。そうすれば利益の3割分は地元に還元される。“カネは天下の回りもの”なので、地域をグルグル循環して、波及しながら地域を潤す。県民所得もあがる。雇用も増えて、地域共同体も強くなる。
そうなれば、全国それぞれの地域が、われもわれもと競うようにエネルギー開発に乗り出すだろう。池の水は滔々と流れていくのだ。このための法律やファイナンスの仕組みが必要だ。
日本は明治以降、近代国家建設をめざして必死に努力した。効率性、生産性を追求して、ひたすら頑張った。その結果、一極集中の国、何かあった時もろい国になってしまった。
国づくりのベクトルを180度転換するときが来たのではないか。「食料自給力を高めること」「エネルギー自給力を高めること」、これで地方が復活する。しぶとく、たくましい、分散自立型の日本に回帰する。
防衛は誰が負担する?
2022.12.26
戦争の姿が変わってきた。大砲やミサイルの前に、宇宙・サイバー・電磁波による攻撃がありうる。仮に、自衛隊の駐屯地や在日米軍基地の電源を断たれたらどうなるか、通信や上下水道・鉄道などが機能不全になったらどうなるか。食料は、医療は…。現実にインフラが破壊され、サプライチェーンが寸断されることを想定しなければならない時代になった。
どうすれば国を守れるか。どんな防衛力が必要なのか。真剣に考えなければならない。
いわゆる安保三文書が閣議決定された。この先5年間の防衛費43兆円は是とするが、上限までただ武器を買い足すという安易な使い方は容認できない。あくまでも、どうすれば国を守れるか、どんな防衛力を構築するか、この全体的な視点に基づいた防衛力整備でなければならない。
財源はどうするか。国債(つまり借金)という声もあるが、私は防衛費に“歯止め”がなくなることを恐れる。かつてわが国は、止め処ない軍拡と、破滅的な戦線拡大でついに国を滅ぼした。それを可能にしたのは戦時国債であった。
防衛費は膨張しやすい。国債に頼ると“歯止め”が効かなくなる。これが歴史の教訓である。だからこそ戦後、財政法は赤字国債の発行を禁じたのだ。歴史を軽んじてはならない。
また、わが国の防衛は、その時々を生きる国民自身のものである。増税をよろこぶ国民はもちろん一人もいない。防衛には負担を伴うが、皆で分かち合うからこそ、国民の意志と自律心が、無謀・無定見な拡大膨張の“歯止め”となるのだ。
わが国防衛力整備のあり方とその財源について、政治家は、国民にまっすぐ向き合って、誠実に説明し、必要とあらば負担を分かち合うことをお願いしなければならない。反発をおそれて逃げてはいけない。
マーケットの警鐘が聞こえるか
2022.11.21
一般に、好景気で金利は上がり、不況で金利は下がる。その理からすれば、金利が極めて低く固定された状況下で経済活動が活発になるはずがない。金利を人体に例えれば体温や血圧なのであり、低体温・低血圧のままでは激しい運動はできない、それと同じだ。
でも今となっては如何ともしがたい。短期2年の奇襲作戦だったはずの“黒田バズーカ”が泥沼にはまってから幾星霜。日銀はもはや金利を上げたくても上げられない現状にある。
ところで、英国トラス政権が退陣に追い込まれたのは、その政策の危うさにマーケットが反応したからだった。つまり、英国ではマーケットは機能したのである。
翻って、日本はどうか。「金利」は言わば官製で、マーケットの評価は反映されない。「株価」も日銀のETF買いで怪しいものだし、最近では高騰対策で「物価」にまで人為的な手が加わる。英国の何倍も深刻な(危機的な)日本においては、すでにマーケットの警鐘すら鳴らないのだ。
いや、一つあった。「為替」である。今の円安は日米金利差などで説明されることが多いが、より本質的にはわが国の歪な財政、金融政策そして国際収支の悪化が背景にある。刹那的な“介入”で何とかなるものではない。
「為替」を通じてマーケットが鳴らす警鐘を、われわれは聞き取れているか。
防衛の試金石
2022.11.16
野党のある政治家が「消費減税の公約は間違いだった」「もう減税とは言わない」と表明して、党内で批判を受けたらしい。氏と話したことはないが、おそらく政治家としての良心が言わしめたのだろう。心中密かにエールを贈るものである。
この世に“打出の小槌”など無い。笑顔でバラマキを続ける政治家は、国民や子孫にまともに向き合っているとは言えない。膨大な借金の山をつくってしまった今日、政治家が財政をどう考えているかは、これまで以上に重要となった。
ところで、先日、少し驚くことがあった。ある人がいきなり電話をかけてきて「増税を語る政治家は許せぬ」と言うのだ。唐突で不正確な主張の背景には、ネットだか何だかの“情報源”があるように感じられた。これまでも、MMT論とおぼしき方々の声を聞くことはままあったけれども、増税はケシカラヌという動きは新しい。
最近このように、増税=悪をことさらに言う声が増えているように感じるのだが、気のせいだろうか。折しも、防衛力強化が国政の重要課題となっているタイミングでの増税悪玉論は、単なる偶然なのか。
東アジアの緊張は否が応にも高まっている。質実剛健な防衛力整備は我が国の急務であり、だから防衛費の増額要請には理由がある。問題は、その財源をどうやって確保するかだ。一部には借金で賄えばよいとの声もあるようだが、借金での防衛力など「張子の虎」である。笑止と言うしかない。財源に裏打ちされた質実剛健な防衛力こそが求められている。
防衛は国民みんなで責任を負うべきものだ。増額分の財源をどこに求めるか。増税をも恐れない覚悟でこの大事な議論に向き合うことができるか。つまるところ、それは、わが国にどれほどの覚悟があるかの試金石となろう。
「防衛力」「抑止力」と「外交力」
2022.10.31
二十代の頃、さる老実業家とお近づきになり様々ご指導頂いた。石川さんとおっしゃる。亡くなられてからもう三十年になるか。
石川さんは、学徒出陣で中国戦線に出征し、そこで終戦を迎える。蒋介石はまさに「仇に対して恩をもって報いる」の態度で何十万の日本兵を粛々と日本に帰還させるのだが、その際の蒋介石の風格に接した石川さんは、中国という国の懐の深さに心底感歎しながらも「空恐ろしさを感じた…」と語っておられた。
石川さんは癌で亡くなる直前、私に遺言を残された。
「いずれ中国は強大になり、アジアの権益をめぐって必ず日本とぶつかります。もし日本がヒステリックになり軍国主義的になって力でぶつかり合うことになれば、そのときこそ日本は亡国。必ず滅びます。中国は底知れぬ国です。私の言ったことを遺言だと思って必ず憶えておいてください…」と。
私は近頃、この遺言を思い出しては噛みしめている。
先々週、北京で中国共産党大会が開かれ、習近平氏に徹底的に権力が集中した。これから中国はますます覇権主義的になり、台湾で何かが起きる可能性も否定できない。東アジア情勢は緊迫している。
たしかに日本は「防衛力」を増強すべきだし、日米の「抑止力」も強化すべきだと思う。しかし「防衛力」「抑止力」ばかりに前のめりになるのは危うい。力での決着は亡国につながるからだ。
「外交」に全力をあげなければならない。外交努力によって諸国との連携を深める。国際社会としっかり組むのだ。それと同時に、中国に平和を訴えしっかりと話をつける。世界を巻き込んででも説得しなければならない。真剣にそして粘り強く。
新しい国際秩序へ
2022.10.14
ロシアによるウクライナ侵略は、重大な国際法違反であり、身の毛のよだつ戦争犯罪だ。21世紀の人類社会は決してこれを許してはならない。
さらにもう一点、21世紀の人類社会が見逃しにできぬことがある。それは、ロシア自身が、国連憲章による集団安全保障への信頼を踏みにじったことだ。
20世紀。第二次大戦後。世界はおぞましい戦争と決別したいと考えた。そして、集団安全保障というシステムで国際秩序を守ることを志した(国連憲章)。そこで特別な力を与えられたのが安全保障理事会の常任理事国(P5)である。つまり、国連憲章の精神あってこそのP5の正統性であり、国連体制だったわけだ。
それなのに、P5の一角であるロシアは国連憲章の精神を完全に破壊した。ならば、もはや第二次大戦後の国際秩序は崩壊した。そう言うしかないではないか。
ウクライナ侵攻勃発後、わが国のとった行動は迅速で明快だった。第一に、資金協力などの人道支援。第二に、ウクライナ避難民の受入れ支援。第三に、国際刑事裁判所(ICC)への支援強化。つまり、国際社会のなかで、「人道主義」と「法の支配」の旗幟を鮮明にしたのだ。
そして先月21日、岸田総理は国連総会において堂々と訴えている。「今こそ国連憲章の理念と原則に立ち戻り、力と英知を結集するときだ。そのために実現しなければならないのが国連の改革であり、国連自身の機能強化だ」「改革に向けて文言ベースの交渉を開始するときだ」と。
「敗戦国」として、どこかしら肩身の狭かった日本。だが、戦後秩序が壊れるタイミングで、歴史的なメッセージを発したことの意義は大きい。
これから、21世紀の新たな秩序づくりが始まる。「人道主義」「法の支配」をかかげて行動する日本には、新秩序建設に参加する資格がある。
日中国交50年に思うこと
2022.6.6
今年9月、日中は国交正常化50年を迎える。この大事な節目において、両国が何を発信するかは重要である。
「日中共同声明」(1972)など、これまでの四つの共同文書はすべて「平和五原則」にのっとっており、これが両国関係の大前提であることは言うまでもない。
だが、約束は守られ、行動にうつされなければならない。「平和五原則」の精神が言葉だけに終わらぬよう、両国関係には一段の努力が求められる。
さて、ロシアのウクライナ侵略が始まるやいなや、国際社会は見事に連帯した。これだけスピーディーに、「力による一方的な現状変更は許さない」「国際法違反、戦争犯罪を許さない」との断固たる姿勢をしめしえたのは、国際社会が、事態を自身の危機として理解したからだろう。
いまや、欧州の安全保障と東アジアの安全保障は別々のものではなく、一体不可分である。わが国も、人道支援や避難民受入れなど独自の動きにすばやく、またG7はじめ国際社会との連携も頻繁である。日米韓、アセアンやクアッドなどとの意思疎通も悪くない。
日本には、防衛力の充実・強化とともに、さらに積極的な平和構築外交が求められている。
わが国のこれらの努力はすべて、インドアジア太平洋を自由で開かれた地域にし、平和と安定を実現することが目的である。それ以外の目的などない。
「ルールに基づく国際秩序、法の支配を尊重すべし」。このメッセージを、わが国はひたすら、繰り返し、繰り返し、呼びかけることが大事だと思う。
日中国交正常化50周年。われわれは、いまいちど「平和五原則」の原点に立ち、その精神を再確認すべきだ。さらに、地域の平和と安定への責任。これを強調することが日中の次なる50年につながると考える。
王道を語る
2022.6.6
“仁者仁道を以て立つ”の孔子を生んだ中国は、王道思想の元祖だ。今日にいたるまで、東洋世界は、なんらかのかたちでこの思想哲学の影響をうける。そんな中国ならば、ロシアを説諭して、蛮行を止められないか。
もし中国にそれだけの器量があるなら、仲裁者として国際的信用は一気に高騰し、その道義的威信は世界最大級となるだろう。だが反対に、中国がこのままロシアへ肩入れしていくとどうなるか。
やっぱり中国は“力による一方的な現状変更”の覇権主義だとして、国際的疑念はいよいよ国際的確信となって確定するだろう。そして、孤立とまでは言わないが、少なくとも中国が国際社会の尊敬を得ることは絶望的となる。
およそ一世紀前。正確には98年前の1924年、孫文は、神戸女学校で“大アジア主義演説”を行う。当時の日本は、ちょうど現在の中国のように覇権主義まっしぐらであった。その日本に対して、孫文は「日本は東洋王道の干城か、それとも西洋覇道の番犬なのか。日本国民はよく考えよ」と説いている。日本への非難であり忠告である。
孫文の言は、まったくもって正しかった。もし日本が領土的野心を捨て、王道を歩んだなら、少なくとも日本は、国際社会に道義大国としての揺るがぬ地位を獲得していただろう。だが、日本は聞く耳を持たぬまま覇道を踏み、そして破滅した。これが歴史である。
一世紀前、孫文が直言したように、今度は、日本が「覇道では破滅しますよ」「ロシアを説得し、ともに王道をめざそうじゃありませんか」と語りかける番だと思う。つまり思想で向き合うのだ。
王道思想は、欧米やイスラム世界にはなじみが薄いかもしれない。けれども仁道あるいは人道主義として説明すれば理解されるだろう。
日中関係は、遣隋使から数えただけでも1400年以上の歴史をもつ。この間、どちらか一方がもう一方から学んだり、あるいは圧迫したりの様々な場面を経験してきた。良い時も悪い時もあったのだ。
中国は永遠の隣国であり、過去から未来へつながる関係性のなかで現在を考えなければならない。今年、たとえ中国に聞く耳がなくとも、日本は王道を説くべきである。それは、永い日中関係における、ひとつの“義理”ですらある。
「世界の平和と繁栄への貢献」(中曽根国連演説)を読む(その1)
2022.5.16
昭和60年(1985年)10月23日、中曽根康弘内閣総理大臣(当時)はニューヨーク国連本部において国連創設40周年記念演説を行っている。わたしは思うところあって、演説録を手に入れて読み、深く感銘を受けた。
世界が物騒になり、皆がどこかしら浮き足立つ今こそ、わたしたちは、あらためて自らの立ち位置と進路について考えてみるべきではないだろうか。ここに演説録の一部を抜粋させていただき、先行きの道標としたいと思う。
『 (前略)
議長
1945年6月26日、国連憲章がサンフランシスコで署名されたとき、日本は、ただ一国で40以上の国を相手として、絶望的な戦争をたたかっていました。そして、戦争終結後、我々日本人は、超国家主義と軍国主義の跳梁を許し、世界の諸国民にもまた自国民にも多大の惨害をもたらしたこの戦争を厳しく反省しました。日本国民は、祖国再建に取り組むに当たって、我が国固有の伝統と文化を尊重しつつ、人類にとって普遍的な基本的価値、すなわち、平和と自由、民主主義と人道主義を至高の価値とする国是を定め、そのための憲法を制定しました。我が国は、平和国家を目指して専守防衛に徹し、二度とふたたび軍事大国にはならないことを内外に闡明したのであります。戦争と原爆の悲惨さを身をもって体験した国民として、軍国主義の復活は永遠にありえないことであります。この我が国の国是は、国連憲章が掲げる目的や原則と、完全に一致しております。
そして、戦後11年をへた1956年12月、我が国は、80番目の加盟国として皆さんの仲間入りをし、ようやくこの国連ビル前に日章旗がひるがえったのであります。
議長
国連加盟以来、我が国外交は、その基本方針の一つに国連中心主義を掲げ、世界の平和と繁栄の実現の中に自らの平和と繁栄を求めるべく努力してまいりました。その具体的実践は、次の三つに要約することができましょう。
その第一は、世界の平和維持と軍縮の推進、特に核兵器の地球上からの追放の努力であります。
日本人は、地球上で初めて広島・長崎の原爆の被害を受けた国として、核兵器の廃絶を訴え続けてまいりました。核エネルギーは平和目的のみに利用されるべきであり、破壊のための手段に供されてはなりません。核保有国は、核追放を求める全世界の悲痛な合唱に謙虚に耳を傾けるべきであります。とりわけ、米ソ両国の指導者の責任はじつに重いと言わざるをえません。両国指導者は、地球上の全人類・全生物の生命を絶ち、かけがえのないこの地球を死の天体と化しうる両国の核兵器を、適正な均衡を維持しつつ思い切って大幅にレベルダウンし、ついに廃絶せしむべき進路を、地球上の全人類に明示すべきであります。……』
「世界の平和と繁栄への貢献」(中曽根国連演説)を読む(その2)
2022.5.16
演説は、「世界の平和と繁栄」への具体的実践として、第一に「世界の平和維持と軍縮の推進、特に核兵器廃絶への努力」をあげたのち、第二に「自由貿易の推進と、開発途上国への協力」、つづいて第三「世界諸国民の文化、あるいは文明の発展への協力」を主張する。世界を相手に王道を説く、堂々たるものだ。そして、さらに格調高く、「新たな文明の創造」を呼びかけるのである。
『 (中略)
議長
いまや、我々の世代の人類は、地球が何億年もかかって用意してくれた我々の生存にとって不可欠の自然環境を自ら破壊しつつあります。土も水も大気も、動物も植物も地球誕生以来もっとも野蛮な攻撃を仕掛けられています。この地球の自殺とも言うべき不条理の中で、少なからぬ地域において、次代を担うべき子供たちを中心に、毎日何万人という人々が飢餓のため尊い生命を失っています。栄養失調や苛酷な条件の中で、肉体や精神の健全な発達に障害を受けている人々は数知れません。これらの地域では世代の欠落すら生じかねないのであります。
我々は、このかけがえのない地球を保持し、人類の生存を維持していくため、新しい地球的倫理とそれを裏付ける制度を生み出すべきだと思います。そして、将来の歴史家が、二十世紀の最後の十数年を、人類史上初めて、人類共存と相互尊重が確立された時期と呼ぶようにしようではありませんか。
我々日本人は、数千年来維持されてきた我々の祖先の固有の思想や生き方を根底とし、その後儒教や仏教に影響されつつ、その思想と哲学を形成してきました。我々の基本的哲学は、古来、多くの詩にこのテーマをうたってきました。私もこれらの詩人にならって、ある夜、一つの俳句を頭に浮かべたことがあります。
天の川わがふるさとへ流れたり
すなわち、我々日本人にとって、宇宙大自然はふるさとであり、これとの調和の中で、生きとし生けるものと共存しつつ生きる……人間も、動物も、草木も、本来は皆兄弟である……という考え方は、きわめて一般的であります。私は、このような基本的哲学を共有する民族はけっして少ないわけではなく、こうした哲学への理解の増進は、今後の国際社会における普遍的価値の創造に大きく役立つのではないかと思います。
もともと人間の潜在的創造力は、地域や民族によって差異のあるものではありません。特に宗教的思索や芸術的直観の世界においては、それぞれの地域や民族の独自性や優秀性が等しく保障されているのを見るのであります。このような文化・文明の多元性の確認による相互評価と相互尊敬の謙虚な態度の人類的な確立こそ、平和の出発点であり、これによってそれぞれの文明や文化はさらに進歩を遂げ、さらにすべての文化や文明の調和による人類の新文明の創造が期待されるのであります。
国際連合は、まさにこのような人類の相互評価・相互尊敬と二十一世紀に向かっての人類文明創造の母体ではないでしょうか。…… 』
「世界の平和と繁栄への貢献」(中曽根国連演説)を読む(その3)
2022.5.16
中曽根総理は、人類史スケールの視点から、今日の「課題」を正確に指摘し、政治家として高い理想を掲げ、希望をもって演説を締めくくった。
世界の抱える「課題」は深刻度を増しているが、なお勇気をふるって、理想をもって向き合いたいと思う。
『 議長、ならびに各国代表の皆さん
明年、1986年は、ハレー彗星が地球にもっとも接近する年であります。前回接近した75年前と比べて、我が地球はどのように変化したでしょうか。たしかに科学技術は当時の人々の想像を絶するほど進歩しました。我が国はじめ数か国は探査衛星を打ち上げ、有史以来謎とされてきたこの天体の秘密はいまや解き明かされようとしています。また、その間たしかに、地球上の植民地主義は順次追放され、民族自決による独立国が急増し、人間の自由と尊厳は、以前に比較して、飛躍的に拡大されてきております。
しかし他方、地球の人類は、科学の進歩によりすでに原水爆というビヒモス(behemoth)を誕生させてしまっております。また、遺伝子操作の発達は、人間の生命の尊厳を危うくするおそれを生み出しています。外と内なる二つの核の脅威にさらされて、人類は、以前にも増して深刻な状況にあると言えるのではないでしょうか。あるいは、飢餓と暴力と差別と麻薬の跳梁をほしいままにさせるだけでなく、かつてない規模の環境破壊を自ら行い、地球上のすべての生物の生存を危うくしながら拱手してはいないでしょうか。
私は、地球上の政治家の一人として、この目前の事実についての大きな責任を感じずにはいられません。
我々は、あの大きな周回軌道をたどって、ハレー彗星が次の世紀の半ばにふたたび地球に接近してくるとき、核兵器の廃絶と全面軍縮を実現した我々の子孫たちがこの彗星に次のように告げることができるよう、ともに努力することを誓い合いたいと思います。
「地球は一つであり、全人類は、緑の地球の上で、全生物の至福のため働き、かつ共存している」と。
ご静聴ありがとうございました。 』
歴史の本流
2022.3.22
歴史は一本の大河のようなものだと思う。滔々たる流れは、ときに澱み、ときに奔流となり、渦を巻き、逆流することもあろう。しかし大河には必ず本流がある。流れに呑まれて身を滅ぼさぬよう、本流を見誤らぬことが肝要である。
たとえば、「戦争の違法化」の歩みなどは本流であろう。第一次大戦、第二次大戦の惨禍を経て、国際社会は不戦条約、国連憲章あるいは国際人道法など、戦争を禁じる法理を積み上げてきた。
ロシアの「力による一方的な現状変更」や「無辜を殺戮する戦争犯罪」「核の威嚇」は、本流を攪乱する激しい渦であり逆流である。それゆえに、遅かれ早かれロシアの自滅は不可避だと思われるが、問題は今この瞬間も無辜の民が犠牲になり、国際秩序が棄損されることだ。
「自由」「法の支配」「基本的人権の尊重」「民主主義」などの諸原理もまた本流である。これら本流に逆らうロシアは、この先、黒い渦に呑まれて沈むしかない。
ところで、新型コロナウイルスと闘うなかで、“迂遠な民主主義より、強権的独裁の方が実効面で優る”との指摘をしばしば耳にする。たしかに、そういう側面も否定はしない。だが、独裁ロシアの愚かさを見よ。わたしたちは、あらためて、本流を見誤る危うさに思いを致すべきだ。
ウクライナにおける人道危機は、国際社会に生きる者すべてに、本流への自覚を迫っている。人類が一歩一歩積み上げてきた精華をここで後退させてはならぬ。
世界史的な危機に臨むに大事なことは、歴史の本流を見定め、国際社会が連帯することである。
国際社会の連帯を
2022.3.21
ロシアによるウクライナ侵略は、「力による一方的な現状変更」であり、国際秩序を破壊し、無辜を殺戮する非道蛮行である。この重大な国際法違反、戦争犯罪を断じて許してはならない。
独立と自由のために力戦敢闘するウクライナ国民に心から敬意を表する。また、蛮行の犠牲となって斃れる方々にただ弔意を表することしかできぬ不条理に義憤を禁じ得ない。
日本政府は、ウクライナやポーランドなど第三国への人道支援はもとより、避難民を積極的に日本社会に受け入れ、生活支援を行うことを決めている。これは、人道上の要請に応えるとともに、国際社会に対してわが国の道徳を明確に示すものである。
国際社会は、一致してロシアの非道を難じ、経済制裁によってプーチン政権を追い詰めなければならない。事態は先行き不透明で、蛮行がエスカレートすることに重大な懸念があり、警戒が必要である。だがこのままプーチンの蛮行がまかり通るようなら、これからの世界は真っ暗闇となる。
人類社会があまたの困苦を経て築き上げてきた「法の支配」などの諸原理や、国際法、国際秩序をここで後退させてはならない。この世界史的な分かれ道において、国際社会は強く連帯すべきである。
これには痛みがともなう。たとえば、対ロシア経済制裁は、国際社会全体にとっても大きなダメージとなりうる。食料やエネルギー価格の暴騰、世界経済や国民生活の混乱もあり得ることだ。政府は、国民の困窮を最小化するために全力をあげねばならない。
ここが辛抱のしどころ。自由な世界を次代に手渡すためみんなで連帯するのだ。
「核兵器のない世界」
2021.8.10
今年もヒロシマ、ナガサキの季節を迎えた。「黒い雨」訴訟の報道をはじめ、今なお原爆後遺症に苦しむ方々の話を聴くにつけ、76年たっても終わらない原爆の惨禍を思い知らされる。
日本は唯一の被爆国だ。核兵器の非を鳴らすのは日本の使命なのだと、あらためて肝に銘じたい。
しかし、日本政府は核兵器禁止条約を締結しようとしない。あれこれ現実を考えてのことだと釈明するが、そこに使命感は微塵も感じられない。もし政府が、本心から「立場の違う国々の橋渡し役」になると言うなら、まず、条約の締約国となることだ。非核の志をハッキリと示さない限り、どこまでいっても日本の主張に説得力は生まれない。
ところで、今年のヒロシマの日は東京オリンピックと重なった。期間中、選手たちが「人種差別」や「LGBT」について自発的に意思表示する場面がみられたが、世界の注目が集まるなか「核兵器なき世界」もなんらかのアピールのチャンスだったかもしれない。
いずれにせよ、今からでも遅くはない。条約を締結し「核兵器なき世界」の旗を高く掲げよう。これは日本の使命なのだから。
コロナ検証委員会を設置すべし
2021.6.22
コロナもかれこれ一年半。ようやくワクチン接種のペースもあがってきた。このタイミングで、これまでのコロナ対策の検証を始めてはどうか。
もちろん終息はまだ先だが、“いずれ”“そのうち”などと言わず、記憶の新しいうちに着手した方が良いと思う。次なるパンデミックは必ずやって来る。コロナ変異株だってわからない。今後のためにしっかり検証し、知見を蓄積することが大事だ。
わたしたち日本人は、“自らの過去について検証し、未来への教訓とする”ということが苦手である。
あの大戦もそうだ。いまも、国家あるいは国民総体としての総括はなされぬままである(一部の優れた試みもないわけではないが)。思うに、先人や仲間のしたことをあれこれ指摘するのは、日本人として辛いことなのだ。けれども私たちは、失敗をくりかえさぬために、勇気をもって“苦手”を克服しなければならない。
見習うべき事例もある。東日本大震災の原発事故では、原因や事故対応の検証のために、なんと四つの調査委員会が設けられた。国会・政府・民間・東電がそれぞれの方針にしたがって検証し、それぞれ報告書を公表している。
新型コロナパンデミックについては、少なくとも、国政調査権のある国会に委員会を設置し、検証作業を開始すべきだと思う。早すぎることはない。
朝のNHKニュース
2021.6.18
今朝7時のNHKニュースに心がゆさぶられた。
ニュースは、都心の米軍基地(赤坂プレスセンター)を取り上げ、米軍ヘリ低空飛行の危険性を指摘して、日米地位協定改定の必要性を論じたものだった。
紹介された日本政府のコメントは相変わらず腰が引けていたが、報道すべきを正面から報道したNHKの姿勢は立派だと感じた。
近年の中国の覇権主義的な動きは目に余る。警戒する世論が高まるのも無理からぬことだ。
ただ気になるのは、対中対決的な“空気”にあおられて、とにかく米軍頼みだという短絡な雰囲気が生まれることである。実際、中国の脅威が増すにつれ、“今は地位協定改定のタイミングではない”という声も聞こえてくる。
しかし、それは逆ではないだろうか。万が一、事故でもあったらどうなるか。事故をきっかけに国民が、地位協定の不平等性・屈辱的内容をひろく認識すれば、それこそ日米関係は一気に不安定化するのではないか。
私はこれまでも、日米関係が大事だからこそ地位協定は改めるべきだと主張してきた。いま、日米の信頼関係がますます重要になっていることを考えれば、地位協定見直しや赤坂プレスセンター返還はむしろ急ぐべきことではないかと思う。
メディア報道の“忖度”についてはよく指摘される(政官界は言うまでもなく)ところだが、毅然と正論を発した今朝のNHKニュースは報道の鑑であり、ジャーナリズムの気概を示すものだったと思う。
世の中の“空気”に流されぬ姿勢に敬意を表したい。
経済安全保障の議論に思う
2021.6.16
国力の源泉たる技術や産業を保護せねばならない。活力を失ったり、他国から奪われたりせぬように、国も企業も大学も必要な手を打つべきだ。これまで、日本は少しのんびり構えすぎたのかもしれないが、これからでも「自律性」「不可欠性」を磨きあげて、強みをより強くすることに注力すべきだと思う。
この、経済安全保障が活発に議論されるのは良いことだ。ただ、気になることがある。
それは、あまりに米中対立を意識してか、議論が情緒的になっていることだ。「米国=味方、中国=敵」という構図にのめり込み、他国の戦略に振り回されているように見える。一番大事なこと(日本の技術や産業を守ること)が二の次になることを心配している。
たとえば、「デカップリング(市場からの中国の切りはなし)」に乗り遅れるな、と前のめりの論調が聞こえてくる。だが、米国は本気でそんなことを考えているだろうか。もしホントウにそうならばことは重大だ。日本は、経済安全保障どころか国家存立の全体構想を描き直さなければならない。
しかし、米中は、激しい技術覇権競争をくりひろげる一方で、経済的には深い相互依存関係にある。米中ともに、甚大な犠牲をはらってまで「デカップリング」に走るとは思えない。
ここをよく見極めることだ。少なくとも現時点では一方的に突っ走らぬ方がよい。トンダ勇み足を踏むかもしれぬから。
ここは冷静になって自国本位に徹するべきだ。世界は広い。米国と中国ばかりが世界ではない。欧州勢だっている。ここで米中の技術覇権競争に巻き込まれることは、構えて避けるべきである。
武道という生き方(その1)~危機に備える~
2021.6.15
わたしの尊敬する武道家はこう言っている。
……「スポーツ選手」と「武道家」とではめざす処が異なる。「スポーツ選手」は、試合当日における最高のパフォーマンスを目標に、練習を重ね、体調を管理してコンディションを整える。一方「武道家」は試合での勝敗を目標としない。いつ何時、いかなる危機に襲われようと闘いそして身を守る。その強さを得るために日々鍛錬するのだ。このように、何を目標とするかによって、心構えも、準備する内容も、すべてが異なってくる。これは、個々の組織や国にも当てはまることだ……。
日本はこれまで、ひたすら経済成長をめざして頑張ってきた。“働き方”であれ、“一極集中”であれ、すべては経済成長というパフォーマンスをあげるためのフォーメーションだったと言える。そのお陰で「スポーツ選手」としてはかなりの成績をおさめることができたのである。
だが、その代償として、何か起きれば国の存立が危ぶまれるほど脆い国になってしまった。たとえば巨大地震で首都機能が麻痺したらどうなるか。情勢不安で食料やエネルギーの輸入が止まったらどうなるか。放漫財政のツケがまわって通貨暴落がはじまったらどうなるか…。
思わぬ危機にもしぶとく持ちこたえ、たくましく乗りこえるだけの強さを、わたしたちは持ち合わせているだろうか。
いま、日本に「スポーツ選手」ではなく「武道家」としての心構えが必要である。
いつ、いかなる危機に見舞われるかわからない。しかし何が起きようと、医療や食料、物流など社会の最低限の機能を維持できるような、たとえ一部が止まっても全体としてはそこそこの経済を持続できるような、そんな打たれ強い国へと組み替えなければならない。
「分散自立」や「食料・水・エネルギー自活」は、これからの日本の新たな国家目標となろう。
武道という生き方 (その2)~抜かない、抜かせない~
2021.6.15
剣・禅・書の達人といわれる山岡鉄舟は「無刀流」を開いた。無刀とは刀を使わないことではない。技ではなく心を鍛えよ、という教えである。
山岡はまた「真の無敵の極所」を求めよとも言った。無敵とはもちろん、オレ様が他の誰よりも強い、という意味ではない。心静かに相手の力量を見極め、刀を抜くことなく勝ちをおさめることをいうのである。
「剣で相手を倒そうと思っている限り、絶対に無敵にはならない。なぜなら敵は数限りなくいるからだ。ところが剣を抜かないのであれば、ある意味、敵はいない。抜かない、相手にも抜かせないというところまでいってしまえば敵はいなくなる(『山岡鉄舟修養訓』平井正修著)」のである。
日本は米中二大国にはさまれている。米中対立が激しさを増すほど、日本は難しい境涯に立つことになる。一歩、道を誤れば国を失うかもしれない。それほど危ういところにいると私は思う。
この窮地から脱しようとして、力に対して力で対抗しようとすれば、結局のところ、力の論理で潰されるしかない。
日本は、「無刀流」でゆくべきである。
自らを鍛えあげ、確固たる理念を磨き、米中抗争には間合いをとり、心静かにその実相を見極める。 「平和国家」「非軍事外交」の国是を貫き、あくまでも「東アジアの平和と安定」に尽力するならば、ここに初めて諸国との連携も可能となり、日本の活路は拓かれる。「アジア共生国家」である。
日本には、こうして「真の無敵の極所」を得るよりほか道はないと思う。
武道という生き方 (その3)~精神的高みに立つ~
2021.6.15
ある武道関係者が、先生と暴力生徒の話に例えて、武道について語っておられた。
『……反抗的な生徒は、先生がいくら言葉で諭しても聞く耳をもたない。ついに、うるせー!とばかり先生に殴りかかるのだが、この先生、武道の心得があってめっぽう強い。生徒は腕をねじあげられ、投げとばされる。なんど挑んでもまるで歯がたたない。やがて、毅然たる先生の前に生徒は素直に心服する。
ここで先生が怒りにまかせて暴力生徒をねじ伏せたのでは、単なる乱闘騒ぎだ。あくまでも、生徒を立ち直らせたいという愛情が大事なのであって、その相手をおもう心あってはじめて、先生の実力行使がゆるされる。この精神的な高みが、相手を心服せしめ、争いを止めるのであり、これこそが武道がめざす処である……。』
やはり力は大事である。決してこちらから先制攻撃をしかけることはないが、相手を撃退するだけの実力は必要である。
わが国は、平和国家・非軍事外交を標榜し、「国際紛争を解決する手段として」武力を用いないことを固く誓っている(憲法9条1項)。こちらから乗り込んでいくことは絶対にしない。しかし、殴りかかられたら、腕をねじあげ、投げ飛ばす。そのために、陸海空自衛隊が日々練磨を重ねてくれている。わが国防の基本姿勢はまさに武道精神そのものと言ってよい。
さらに大事なのは、相手のためをおもう心だ。相手よりも精神的に一段高い処に立っていなければ、同レベルの暴力に堕するばかりで、敵意が消えることもない。攻撃は反撃を呼びまたその反撃を生んで、争いは止むことがない。人の世は多分にそういうものだろう。
けれども、われわれの先達は、争いの連鎖をくいとめるために、みずからが精神的な高みをめざしたのだ。戦いにおいてすら相手を思いやる。この高い精神性あってこそ、真に争いを終わらせ、平和を実現することができるのだ。先達はこうして共存の知恵を、武道という生き方にまで昇華させた。
日本を取り巻く国際環境は厳しい。だが、他国と向き合う際、わが国は一段の精神的高みに立つことが大事だ。これは先人先達の教えでもあるのだ。
過去から現在そして未来へつづく歴史のなかで、しかもこの激動の世界において、日本が与えられている役割とはいったい何か。あらためて静かに考えるとき、私たち日本人にはこの“宝刀”のような精神文化のあることに気づく。
「人類の平和と調和」という理想をかかげ、武道という生き方を体現しながら国際社会で生きる。これこそが日本民族の役割ではないかと思う。
「財政民主主義」と独立財政機関
2021.6.10
これまで、「国はいくら借金しても大丈夫だ」という珍説(そんなことあるわけがない)を耳にするたびに苦々しい思いをしてきた。けれども、コロナパンデミックからこちら、「財政は大丈夫なの?」と心配するお声をよく聞くようになっている。これは国民のみなさんが、理屈ではなく、何かしら本能でもって危機を感じておられるからではないか。
日本の財政はかなり危うい。世界のどの国とも比較にならぬほど、ダントツぶっちぎりに悪い。なぜ、これほどまでに悪いのか。それはズバリ、われわれ政治家つまり国会が責任を全うしていないからだ。
憲法は「財政民主主義」を規定している。つまり国民の代表たる国会に、政府の財政運営をチェックする役割を与えているのだ。だが、国会がその要請に応えられていない。
財政が破綻してヒドイ目にあうのは国民である。国民にヒドイ思いをさせないために、国会はみずからの責任において「財政民主主義」を機能させなければならない。
その志のもとに、本日、国会内に「独立財政推計機関を考える超党派議員の会」が発足した。国会が、国民への責任を果たすため行動を開始するのだ。きっと国民は支持してくれるものと信じている。
日本を除く、すべての先進国は独立財政機関を持っている。ひとり日本だけ機関を持たぬことと、ひとり日本だけダントツに財政が悪いこととは、決して無関係ではない。
中国にどう向き合うか(その1)~孫文の大アジア主義演説~
2021.4.8
いまやスーパーパワーとなり、覇権主義的な傾向を強める中国。この中国にどう向き合うべきか。
わたしは、孫文のいわゆる大アジア主義演説(1924年・神戸)にヒントを見出している。
孫文は演説で、『今後日本が世界の文化に対して、西洋覇道の番犬となるか、あるいは東洋王道の干城となるかは、日本国民の慎重に考慮すべきことである』と説いた。日本に、力による『覇道』ではなく徳による『王道』を行けと迫ったのだ。
しかし日本は聴く耳を持たず、軍事力にモノを言わせて山東出兵、満州事変そして日支事変と『覇道』を突き進み、結局のところ、世界に孤立して、破滅した。
言うまでもなく、孫文の演説は、日本の覇権主義への痛烈な非難なのであった。だが、これを現在にあてはめれば、そっくりそのまま、今日の覇権主義中国への鋭い警告のようにも聴こえる。
ところで、戦後日本は一転して平和国家・非軍事外交を標榜し、軍事力ではなく、国際法やルールにのっとり国際協調を重んじた。自由貿易の恩恵もあって経済的繁栄を獲得し、国際貢献にも汗をかき、国際社会の信頼を得ることができた。
日本は、『覇道』に走って大失敗をしたが、その後『覇道』と決別したことで成功を収めたわけである。
1924年の孫文の胸中を思いつつ、日本はいま、中国に『覇道』の愚を説くべきである。中国に、同じ轍を踏ませぬために。
そして日本自身もまた、「日米同盟で中国を封じ込めよ!」などと短絡に走らぬことを、みずから肝に銘じなければならない。力で力を屈服させようとの発想は、しょせんは『覇道』でしかないのだから。
中国にどう向き合うか(その2)~中国の覇権主義~
2021.4.8
東シナ海や南シナ海を自国の「管轄海域」だと称して、一方的に権利主張する中国。そのふるまいは、国際法をないがしろにするものである。
しかも、「強軍思想」を掲げ、矢継ぎ早に軍事関連法を整備し、軍備を増強するのだから、国際社会が警戒心を深めるのは当然すぎるほど当然である。
尖閣諸島での領海侵入もエスカレートしている。日本はこれまで、海上警備という国内法の枠内で対処してきたが、状況はもはやそれを許さないように思う。日本が主権侵害を看過しないことを、中国にしっかり伝える必要がある。
また、国際社会とも連携して、この理を明確に示すことが重要だと思う。独り善がりが世界の目にどう映っているか、中国は理解すべきである。
それにしても、これほどの大国が、傍若無人にふるまって平然としているのも不思議である。国際社会と手広く付き合うには「国際法」を遵守した方が何かと都合がよいはずだ。それなのに、あえて波風を立ててまで覇権主義・膨張主義に走るのはなぜか。
考えられる理由のひとつに、「国際法」に対する中国独自の理解のしかたがあるかもしれない。
そもそも、中国における法治主義とは、国家(共産党)が法令を使って人民を統治することを指す。国内法ならば「これが中国流なのだ…」で通るだろう。しかし中国流法治主義を国外にも適用しようとすれば、当然のことながら「国際法」とのバッティングは避けられない。
中国は、海洋においても、中国流法治主義が通用すると思っているように見える。ただそのように思い込んでいるだけかもしれないし、確信犯として「国際法」秩序に挑戦しているのかもしれない。だが、いずれにしても中国は「国際法」を無きものにすることはできない。
あるいは、覇権主義は「中国の夢」ナショナリズムの発露として、抑制がきかないのかもしれない。
だとすればそれは周辺国にも、また中国自身にとっても、たいへん不幸な結果をもたらすだけである。力による『覇道』は必ず行き詰まり、破綻するからだ。
わたしたちは中国に『覇道』の愚を説かねばならない。もちろん中国は「アジアに侵略した日本がそんなことを言えるのか」と反発するだろう(当然だ)。けれども『覇道』ゆえに破滅した日本の言には切実があるはずだ。自らの非を非と認めた上で、大誠意をもって『覇道』の非を鳴らすのだ。
日中関係は少なくとも千五百年以上にわたる長い歴史をもつ。中華思想も、華夷秩序も、帝国主義時代の中国の屈辱と苦難の歴史も、日本は実経験を通じてよく知っているはずだ。
ならば、「なぜ中国がことさらに国際法秩序に挑戦的なのか」「なぜ覇権・膨張主義的にふるまうのか」について、その知見をもって分析し、深層心理を探求し、説得の糸口を発見することもできるのではないか。
中国にどう向き合うか(その3)~米中対立と日本~
2021.4.8
米中対立が激しさを増している。板挟みになったかっこうの日本は、いかにあるべきか。
米中対立の実相は覇権争いであり、国益と国益のぶつかり合いである。ということは、利害さえ一致すれば両国はいつでも妥協しうると考えなければならない。実際、分野によって両国が協調協力している事例は少なからずある。
ハッキリしているのは、この覇権争いに第三者が立ち入る余地はない、ということ。どちらかに肩入れしてもいつハシゴをはずされるかわからない。下手をすれば国を失うかもしれない。
したがって、どんなに苦しくとも両大国とは一定の距離をとる。そして近隣諸国と連携しながら、東アジアの平和と安定を模索する。これを日本外交の大方針としなければならない。
ところが、先月開催された「日米2+2」(外交防衛閣僚会合)で、日本は、米国とともに中国を名指しで牽制し、米側に立つことを鮮明にしてしまった。
第三者立ち入るべからずの禁を犯すばかりか、米中の調整役を担うべき日本が、みずからその任を放棄したも同然である。東アジア激動の歴史的場面において、わが国は舵取りを誤った可能性がある。深く憂慮せずにはいられない。
日米関係の重要さはもちろん認める。しかし、だからといって、必ずしも中国に対する政策で日米両国が一致せねばならぬものではない(韓国をみよ)。
「日米同盟で中国を封じこめる」との戦略がそもそも非現実的であるばかりか、かえって対立を煽り、日本をして軍拡の罠におとしめる危険をはらんでいることは、どんなに声を大にしてもしたりないほど重大である。ここで前のめりになることは、日本にとっておそろしく危険な選択である。
むしろ、米国には、日本が中国との独自の回線を持っていることを強調すべきなのだ。足並みを揃えるだけが能ではない。「日本は日本のアドバンテージを活かした貢献をする」と自信をもって言えばよい。
わたしたちは今、過去から現在をまたいで未来にいたる、超・超長期的な視野をもって「国益」を熟慮すべきである。日本は東洋の国であり、わたしたちにはアジアの血が流れている。大昔からそうだったし、これからもそうだ。
わたしは基本的にアジア主義であるから、アジアの平和と安定を希求してやまぬ。ゆえに、中国に対しては「覇権主義は決してためにならない」と語りかけ、米国に対しては「日本なりのやり方で東アジアの平和と安定に尽力する」と言いたい。それが、米中対立時代における日本の役割だと信じる。
中国にどう向き合うか(その4)~「平和五原則」の再確認~
2021.4.8
戦後、日中間では四次にわたって共同文書が合意されてきた。
まず1972年国交回復時の『日中共同声明』、次に1978年の『日中平和友好条約』。そして江沢民主席が来日した1998年の『共同宣言』(小渕首相)。さらに2008年の胡錦濤主席来日時に合意された『共同声明』(福田首相)だ。
これらに一貫して通底するのは「平和五原則」の精神である。すなはち「主権及び領土保全の相互尊重」「相互不可侵」「内政に対する相互不干渉」「平等互恵」「平和的共存」であり、これらは国交回復以来の日中関係の大前提と言うべきものである。
中国の覇権主義に不信感と警戒感が高まりつつあるが、いまこそ、あらためて「平和五原則」が再確認されるべきである。
日中両政府は、「平和五原則」の精神にしたがい挑発的行為を抑制すべきことを盛り込んだ「第五の文書」をめざしたい。
習近平主席の来日がひとつのチャンスではなかろうか。おりしも、来年には北京冬季五輪が開催されるし、日中関係も国交回復から50年の節目を迎える。この機をとらえて、日中関係の原点に立ち返ることの意義は大きい。
中国にどう向き合うか(その5)~日本の志~
2021.4.8
大隈重信によれば、チグリス・ユーフラテスに発祥した人類文明は、かたや東へ展開して発展をかさね日本列島へと至り、かたや西に発展して大西洋を越えさらに太平洋を越えて日本に至った。かくして日本は東西文明合流の地であり、したがって日本人は両文明をよく理解しその調和を図る大使命を持つ、とする。
わたしはこの大隈の見立てに共感する。現下の日本は、米中の板挟みにあいつつも、両者の通訳・仲介・調整の役割を与えられようとしているが、それも偶然ではないように思う。詳しい方にご教示いただければありがたいが、何か地政学的な必然なのではあるまいか。
いずれにせよ、米中がうまく調停され、両文明の調和が成れば、西洋近代を超克する新しい時代が拓かれるかもしれない。
夜郎自大にモノを言うつもりはないが、少なくともわが国は、このような世界史的視野からの使命感と目標、つまり志をもつべきだと思う。
目先の出来事に忙殺されると人は大局観を失う。そうならぬためにも志をもつことは大切である。世界の流れをよく見極め、志をもって歩むことは、歴史の本流に身をおくことであり、結果的に自身の身を守ることになると思う。
志をもって進む日本であってほしい。
それにしても、中国の勢いはすさまじい。いったいどこまで膨張し拡大するのか。そらおそろしさを感じる。
しかし中国も、2045年頃には急激な人口減少局面に移行する。中国もそれが分かっているからこそ、今ことさらに覇権主義に走るのかもしれない。
日本は中国の覇権主義に脅威を感じながらも、経済的には深くて太い関係を築いている。中国もまた世界との関係あっての大国であり、孤立しては国を維持できぬことくらい中国自身がよくわかっていよう。
日中はお互いの共存繁栄のために、東アジアでイーブンの落ち着いた協力関係を築くしかない。
加えて、世界が文明史的転換期を迎えている今、日中は人類共通の利益のためにも汗をかくべきだと考える。
まず手始めに、地球環境問題で日中提携はどうだろうか。
“アメリカ・イズ・バック”
2021.2.22
“アメリカ・イズ・バック”。ハリウッド映画のセリフみたいなフレーズとともに、米国が「パリ協定」に復帰した。いいことだ。“ウェルカムバック”である。
そもそも、世界一の経済大国であり、世界二位の温暖化ガス排出国である米国が、「パリ協定」から離脱したこと自体が、まったくヒドイ話だったと思っている。指導者たるべき国が“自分さえ良ければいい”とばかりに国際社会に背を向けたのだから、ここで失われた米国の威信は小さくなかった。
バイデン大統領の英断を機に、「パリ協定」がより強力なものになればいいと思う。
さらに、バイデン大統領は「イラン核合意」復帰の可能性にも言及している。
今度の米国vsイランの緊張は、もとはと言えば、米国が一方的に「イラン核合意」から離脱して始まった。まずは、混乱を招いた米国が事態収拾に動くべきだろう。
しかもこの件では、わが国も海自艦を派遣するなど、深く関わってしまっている。日本も当事者なのだ。バイデン大統領の思い切った政策転換を強く望む。
核といえば、より深刻なのが北朝鮮だ。
決して平坦な道のりではないだろうが、朝鮮半島の非核化をなんとしても実現しなければならない。バイデン大統領には、大度量と大信念をもって、実効的な「米朝協議」を主導していってほしい。
もちろん、米国任せにするわけではない。「米朝協議」が前進するよう、日本も大いに汗をかくのは当然のことだ。非核化を後押しする多国間枠組なども考えるべきだろう。北東アジアの平和と安定、朝鮮半島の恒久的な平和体制は、日本の最大級の国益なのだから。
東京オリンピック・パラリンピック
2021.2.18
JOC会長辞任劇はお粗末というほかないが、あらためてクーベルタン男爵の五輪精神に関心が集まったのは思わぬ副次効果であった。ならば、これをきっかけに、商業主義に走り過ぎたオリンピック・パラリンピックのあり方について、一歩も二歩も踏みこんではどうだろうか。
開催まで半年をきった東京大会だが、アンケート調査では国民の7割以上が「中止」や「延期」と回答する異常事態となっている。しかも昨日は某県知事の中止発言も飛び出して、いっそう不透明感が深まった。
一刻も早く、国民に向けて、世界に向けて、主催者は東京大会開催への確固たる決意を示さなければならない。
その際、徹底したコロナ対策、つまり、科学的・医学的知見の粋を集めた“日本スタイル”を明確にアピールすることが何より重要だと思う。
すなわち、無観客を原則とし、必要ならば競技種目の絞り込みも辞さない。海外からの入国はアスリートと関係者に限る。選手団を送らぬ国があっても無理強いはしない。あらゆる場面での感染防止に万全を期す。そしてこの際、チケット販売収入や経済的な利害得失については考えない。
質実剛健な競技大会と、徹底したコロナ対策を、立派に両立させる。これが“日本スタイル”だ。
“日本スタイル”で開催すれば、過度の商業主義に陥った現代オリ・パラは、結果として五輪精神の原点に戻ることになる。いや、そもそも地球温暖化や新たなパンデミックの可能性など考えれば、華美に過ぎる五輪はすでに開催不能となっていたのかもしれない。
“日本スタイル”の東京大会は、古い五輪に「引導を渡し」、新しい五輪に「先鞭をつける」ものとなるだろう。
こうして、徹底した準備をすすめた上で、コロナ情勢をよく見極めることは重要である。仮に、やはり開催は困難だと判断される場合においては、潔く、断念する。この覚悟ですすむべきだと私は思う。
大深度地熱発電
2021.2.15
珍しくもなくなったスーパー台風、梅雨の集中豪雨、夏の酷暑…。そして、世界で頻発する洪水、干ばつ、熱波、森林火災…。地球温暖化は、わずか1℃の気温上昇でこれほどの気候危機を招いている。わたしたちがこのまま何もしなければ、今世紀末には気温は5℃近く上昇するそうだ。そうなれば、大災害や海面上昇、食料不足、水不足で人類の生存はいよいよ危うい。
気温が上昇して、ある限界点(ティッピングポイント)を越えると、後戻りのできない破滅的な段階に突入する。手の打ちようがなくなる。このティッピングポイント、2℃上昇から3℃上昇の間だろうと言われているが、何としてもこれだけは避けたい。
この危機感あればこそ世界は、パリ協定(2015年)で温暖化ガス排出をゼロにしようと合意した。日本も先日、「2050年までに排出ゼロ」と国際公約したばかりだ。しかしながら、たとえ日本や世界各国が目標を達成してもティッピングポイントを回避できるかどうかわからぬそうだ。わたしたち人類は、それほど危ういところにいる。
いずれにせよ日本は、少なくとも2050ゼロカーボンは達成しなければならない。そのためには、化石エネルギーから再生可能エネルギーへの大転換が必須となる。が、容易ではない。電力の8割弱を担う火力発電を30年足らずでゼロにするというのだから、並大抵のことではない。けれども、総力をあげて、ありとあらゆる再エネ増産にむけて果敢に挑戦する以外に道はない。
ところで、日本は世界有数の地熱資源大国で、原発23基分の資源量をもつとされる。しかし、もったいないことに、ほとんど未活用のままだ。季節や天候、時間帯で不安定になる太陽光や風力、水力と違って、地熱発電は地球内部エネルギー由来なので安定電源となりうる。地熱発電は「宝の山」であり、放っておく手はない。
次世代型の「大深度地熱発電」の研究・開発がすすめられている。これまでの地熱発電(地下1~2㎞)よりも、さらに地下深く(地下3~5㎞)の地熱エネルギーを活用するのが「大深度地熱発電」だ。
原理はいたってシンプルで、高温乾燥岩体(ドライロック)の熱を直接利用する。したがって、通常の地熱発電のように地下の熱水や蒸気を探し当てる必要がない。実用化されれば、地球上のどこでも(火山国でなくとも)大深度地熱で発電が可能となる。つまり人類は、無限の脱炭素エネルギーを手にすることになるのだ。
大深度地熱発電なんか「宝くじ」を当てるようなもの…と笑われるかもしれない。だが、「宝くじ」は買わなければ当たらない。そして、もし当たったら…大深度地熱発電は、『地球温暖化の逆転ホームラン』となるだろう。
分散自立国家論 ~昔から分散自立だった~
2021.2.8
幕末には280近い藩があった。それぞれが地域資源をフル活用しながら、「食料」「エネルギー」を自活した。日本は昔から分散自立型だったのだ。
明治になって、富国強兵・殖産興業が国家目標となった。ひたすらモノを生産し、輸出し、稼いだ外貨で国に投資した。戦後もこの流れは変わらず、効率性を追求して懸命に頑張った。おかげで経済成長をなしとげられたが、そのかわり日本は一極集中型の国になった。
しかし、やっぱり一極集中はもろい。日本が世界で稼ぎまくるには都合良かったが、何かあったときの復元力とか、持ちこたえる底力とか、国を守るとかいう意味では、とても心もとない。
食料も同様だ。輸入した方が安くて効率もいいから…と、わたしたち日本人は食料の半分近くを外国に頼るようになってしまった。だが今はよくても、国力が落ちれば買いたくても買えぬ。
効率ばかり追いかけたら脆弱な国になった。もう一度、分散自立の日本にもどせないか。近代化以降の、一極集中に象徴される国造りのあり方を、ここらで丸ごと見直せないか。
あの田中角栄元総理ですら実現できなかった列島改造だが、今ならできると思う。なぜなら、時代の価値観が変わりつつあるからだ。
たとえば、地球温暖化をくいとめるには、わたしたち自身がこれまでの生き方や価値観を改めなければならないが、もうすでに時代は変わり始めている。効率最優先の企業行動ですら、「ESG金融」にみられるように大きく変わってきたし、グレタ・トゥーンベリさんら若い世代の声も確実に大きくなりつつある。こうしている間も、時代の価値観は刻一刻と変わる。
効率優先で築いてきた一極集中という国のかたちも、そろそろ分散自立型へ回帰するときではないか。
分散自立国家論 ~法律、税制、ファイナンス~
2021.2.8
分散自立型に回帰するには、全国のあちらこちらに、足腰の強い地域社会、しっかりした自立経済が復活しなければならない。その復活のカギは、「食料」「エネルギー」が握っている。
というのは、いま半分近くを輸入に頼る「食料」は、この先、国内自給を高めざるをえないのだし、「エネルギー」もまた再生可能エネルギーへの切り替えが決まっている。要するに、これから「食料」「エネルギー」の国産化が国家的大目標となる。
そして、その担い手は地方だ。「食料」「エネルギー」生産による利益が、産地に還元されるよう仕組むことによって、地方の意欲を喚起し、増産の流れをつくらなければならない。
デンマークでは、風力発電所を建設するとき少なくとも15%の地域資本を入れるよう法律で決まっている。したがって、生み出される便益の少なくとも15%は地域に還元される。こうして還元されたカネが、グルグルと地域を循環しながら波及し、雇用を生み、地域経済の自立度を高める。
要は、エネルギー生産を地域振興に直結させること。そしてそのためには、創出された便益を地域に還元させる法律、税制、ファイナンスの仕組みが決め手となる。
日本列島には、かなりの再生可能エネルギーのポテンシャルがある。地方がこれを上手に活かすことができれば、自立した地域経済がうまれ、足腰の強い地域社会が再建できるだろう。そんな地域が、全国に何十ケ所、何百ケ所と存在する姿こそが分散自立だ。再生可能エネルギーばかりではない。食料生産もまた重要な柱となって分散自立を支えるだろう。
分散自立型の日本になったなら、もし仮に、何らかの理由で東京が麻痺しあるいは一極集中のシステムが機能しなくなったとしても、日本は生き延びることができる。次の世代に、日本を手渡すことができるのだ。
分散自立国家の建設は決して不可能ではない。これは、新しい時代を拓くための、わたしたち日本人の挑戦である。
それにしても、懸命に稼いだカネで、ソックリそのまま巨額の「食料」「エネルギー」を輸入する日本。働けど働けど豊かさを実感できないのは、こんなところにも理由があるのかもしれない。だが、ひたすら効率性を追いもとめ我武者羅にガンバってきた時代も終わる。
ときおり、豊かさとは、幸せとは何だろうと考える。おこがましいことを言うつもりはないが、少なくとも、「足るを知る」ことや、自立した地域社会で助け合って暮らすことで、わたしたちは落ち着いた豊かさを取り戻せるのではないか。
分散自立の日本に回帰することは、たくましい国を取り戻し、真の豊かさを取り戻すことだと思う。
ファイブ・アイズ
2021.2.3
ファイブ・アイズとは、アングロ=サクソン系5ケ国(米・英・加・豪・ニュージーランド)による機密情報共有の枠組みであり、サイバー同盟の性格をもつ。
昨年来、某閣僚が日本もこれに加盟すべきだとの発言を繰り返している。現実には諸事情あって日本の加盟は不可能に近いらしいが、それでも公的立場にある閣僚が国民にむかって、あるいは世界にむけて公言をつづける以上、わたしも一国民として考えを明確にしておかなければならない。わたしは、ファイブ・アイズ加盟に反対である。
理由のひとつは、わが国の自主独立が危ぶまれることだ。
機密情報は一国の安全保障にかかわる。他者に委ねたり、握られたりすれば、国の自立自存を危うくする性質のものだ。独自の本格的な情報機関を持たず、この分野において脆弱なわが国が、仮に枠組みに参加すればどうなるか。日本がただ一方的に機密情報を依存し、結果として彼らのコントロール下におかれるであろうことは想像に難くない。
敗戦によって主権の一部を放棄し、安全保障を米国に委ねる日本が、たとえ加盟したとて、“対等互角”な関係など夢のまた夢である。従属がより深刻に、より決定的になるだけだ。しかも、一度加担したら二度と足抜けできない。日本の独立は永久に困難となる。
また、加盟は、彼らと軍事的に一心同体化することを意味する。仮にそうなれば、敵に回すのは中国・ロシアばかりではない。大陸欧州、アジア諸国はじめ世界各国との間にも大きな距離をつくり、かつ固定化してしまう。
日本は東洋の国、アジアの一国だ。自主自立の気概をもち、国際社会の一員としての責任を果たし、品格を示すことこそ日本の進むべき道である。それを、わざわざ逆行して、世界との交際関係を狭めるようなことをして、いったい何の利があるというのか。
“腕力の強いグループに追従しておこう…”などという卑屈で怯懦な考えならば、たとえ加盟しても“グループ”内で尊敬は得られない。そればかりか、世界からは軽侮を招き、結局は孤立するだけである。
ザッと考えただけでも、ファイブ・アイズ加盟によって、わが国はこれだけの致命傷を負う。それでもなお、国を利して余りあるだけの加盟の意義が、一体全体どこにあるというのか。
ワクチン。ワクチン。ワクチン。
2021.1.30
WHOの緊急事態宣言から一年。わが国でも、なお深刻な事態が続いている。
感染拡大が始まったときから、PCR検査をもっと自由に、もっと手軽に受けられる体制をつくるべきだった。ウイルスと戦うのに、どこに“敵”が潜んでいるか不明なまま戦えるはずがないからだ。
WHOテドロス事務総長が世界に向けて「テスト。テスト。テスト。」と訴え、時の総理大臣が「検査を増やすよう指示しております…」と答弁するのに、それでも充分な検査体制が整わないのは何故なのか。いずれかのタイミングで必ず、PCR検査含めあらゆるコロナ対策が、これで良かったのかどうか、キッチリと検証されなければならない。
それはともかく、今は「ワクチン。ワクチン。ワクチン。」である。
まず、何をおいてもワクチンの“確保”に総力をあげることだ。政府は、製薬会社と並々ならぬ気迫で交渉し、早期入荷を確実にしてほしい。
さらに、ワクチン接種の“スピード”も大事である。報道されているような、広い体育館で注射の順番を待つようなやり方ではとても追いつかない。インフルエンザ予防接種のように、かかりつけ医や診療所でも接種できるよう、医師会に協力をお願いすべきではないか。また、高齢者施設に出かけて行って接種し、自衛隊は各駐屯地にお任せする、というような柔軟な工夫も必要だろう。ここは、杓子定規にならぬよう、型にハマらぬよう注意した方がよい。
地球温暖化と食料 ~ サツマイモ基腐病 ~
2020.12.18
三年ほど前から、南九州でサツマイモ基腐病が発生するようになった。残渣処理や客土などさまざまな試みもむなしく、基腐病はいまや九州のみならず四国や関東にも拡がるに至った。いま全国で、サツマイモの産地存続が危うくなっている。
調べると、世界では古くからある病気らしく、各国それぞれ工夫をして上手に付き合っているのだという。日本でも、たとえば交換耕作に取り組むなど、思い切った対策で臨むべきだ。
高カロリーのサツマイモは重要な戦略穀物である。わが国の食料安全保障のためにも、サツマイモ生産は絶対にあきらめてはいけない。
今回のまん延の背景には、やはり地球温暖化がある。サツマイモに限らず、食料生産が地球温暖化への「適応」を迫られているのだと直感する。
「気候非常事態宣言」、採択さる
2020.11.25
日本は、中国や米国よりもはるかに温室効果ガス削減に実績をあげている。それなのに、昨年11月のCOP25では日本が集中砲火をあびてしまい、何とも釈然とせぬ思いが残った。
ここは、あらためて日本の強いメッセージが必要だ!との思いから、今年2月、超党派の国会議員によって、「超党派『気候非常事態宣言』決議実現をめざす会」が設立された。
その準備が実り、先週19日に衆議院で、翌20日には参議院で、それぞれ『気候非常事態宣言』が決議された。
先日の、政府による2050カーボンニュートラル宣言につづいて、国会でも「脱炭素」への決意が示されたかっこうだ。政府、国会、ともに気候危機に立ち向かう覚悟を世界にメッセージしたのだ。
さあ、これから、具体的な取り組みに全力をあげることになる。日本人の力量を世界に示すときだ。
気候非常事態宣言決議
近年、地球温暖化も要因として、世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曽有の被害をもたらしている。我が国でも、災害級の猛暑や熱中症による搬送者・死亡者数の増加のほか、数十年に一度といわれる台風・豪雨が毎年のように発生し深刻な被害をもたらしている。
これに対し、世界は、パリ協定の下、温室効果ガスの排出削減目標を定め、取組の強化を進めているが、各国が掲げている目標を達成しても必要な削減量には大きく不足しており、世界はまさに気候危機と呼ぶべき状況に直面している。
私たちは「もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて気候危機の状況に立ち至っている」との認識を世界と共有する。そしてこの危機を克服すべく、一日も早い脱炭素社会の実現に向けて、我が国の経済社会の再設計・取組の抜本的強化を行い、国際社会の名誉ある一員として、それに相応しい取組を、国を挙げて実践していくことを決意する。その第一歩として、ここに国民を代表する国会の総意として気候非常事態を宣言する。
右決議する。
気候危機に、立ち向かう。
2020.10.28
世界各地で、記録的な熱波、大規模な森林火災、ハリケーンや大洪水が頻発し、著しい被害をもたらす。わが国でも、数十年に一度といわれる台風や豪雨が毎年のように発生している。まさに、気候危機である。
国際社会は、パリ協定のもとで、温室効果ガスの排出削減に取り組んではいる。しかし仮に、各国がそれぞれの削減目標をすべて達成したとしても、進行する地球温暖化をくいとめるには至らない。
もはや、人類の生存すら脅かす地球温暖化。乗りこえるためには、われわれ人類が「脱炭素社会」を創りあげる以外にない。
26日、菅首相は所信表明演説において、「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現をめざす」と高らかに宣言した。
続いて本日、議員連盟『超党派「気候非常事態宣言」決議実現をめざす会』が、宣言決議案の文案を正式に決定した。この国会中の、衆・参両院における国会決議をめざして、これより行動を開始する。
全世界にむけて、気候危機に立ち向かう決意と覚悟をしめしたい。
日本と韓国、共通の志
2020.10.20
米ソ冷戦は、世界を分けたイデオロギー対立であった。日本は、迷うことなく西側陣営に属したし、その判断は正しかった。
ところで、今回の米中対立はイデオロギー対立ではない。国益と国益のぶつかり合い、つまり覇権争いがその実相である。なので、利害さえ一致すれば米中はいつでも手を握ると考えておかねばならない。よって、覇権争いの外にいる第三者は、不用意にかかわってはならぬ。下手に一方へ過剰依存したり、一体化などと言って深入りすれば、国を失う破目に陥る。
米中対立がエスカレートするなかで、日本のとるべき道は、「米中のどちらに与するか?」ではなく、「米中どちらにも与しない」という独立自尊の自立路線である。この選択肢しかないことを、厳しい覚悟をもって胸に刻むべきである。
同じく、米中二大国に挟まれたかっこうの韓国にも、同様のことが言えるはずだ。日本にとっても、韓国にとっても、米中覇権争いの渦に呑みこまれぬことが何より肝要である。わたしたちは今、日韓「連携」こそが日韓共通の「利益」であることをハッキリと認識すべきだと思う。
それにしても、日本と韓国のいがみ合いには眼を覆うばかりだ。何か事が起こるたびに両国世論が沸騰しさらに関係が悪化する、という負のスパイラルに陥っている。もう、このまま放置するわけにはいかない。
負のスパイラル構造から脱け出すために、ここで一つの提案をしたい。
それは両国が、一致せぬことより一致することに力を注ぐことである。「対立」「いがみ合い」よりも「連携」「利益」に眼をむけるのだ。
大きく変わりつつある北東アジア情勢だが、ここに“平和と安定”を築くことは、日本にも韓国にも死活的に重要な利益であるはずだ。日韓が「連携」して、北東アジアにおいて日本・韓国・中国・米国・北朝鮮・モンゴル・ロシアの七か国による多国間協議、ひいては集団安全保障の枠組み構築をめざすのだ。“北東アジアの平和と安定”という志を共有したとき、われわれは文字通り“同志”となれるだろう。
先日、日本と韓国の学者・政治家によるオンライン会議が行われた。そこでの小倉和夫氏(元駐韓国大使)の言葉が胸に響いた。
『日韓はテーブル越しに向き合っているのではない。横に並んで座っているのです。テーブルの向こう側は世界であり、日韓はともに協力して世界と向き合うべきなのです。』と。
新しい「列島改造論」
2020.10.16
『日本列島改造論』を掲げた、あの田中角栄元総理ですら為しえなかった“一極集中の是正”だが、今なら、ひょっとしたら、できるかもしれない。そう感じるのは、時代が大きく変わってきたからだ。
産業革命以来の、効率性重視の西洋近代文明が行き詰るにしたがって、世界中が、なにか新しい“価値”を見出そうとしているようにみえる。その“価値”とは、効率ばかりでは得られない何か、効率を追求したために失った何かだと言えようが、ここでは深入りしない。
とにかく、効率性追求の必然たる「一極集中」は、“効率性が全て”でなくなれば、また変わりうる。日本においても「一極集中型」から「分散自立型」へと列島改造のチャンスが出てくる。
「分散自立型」とは、日本列島の随所で、地域社会がたくましく自立している姿だ。自立に何が必要かというと、まず何と言っても、生産活動、富の創出だろうと思う。シンプルに考えて、人の生存に不可欠な物資は「水」「食料」「エネルギー」だから、これらの自活が目印とされてしかるべきだ。幕藩時代の藩経営がそうだった。当時、「食」も「水」も「エネルギー」も完全自活が要求されたはずだ。
幕藩時代にもどろうとまでは言わないが、たとえば地方自治体は可能な限り、自給率を高める努力を義務付けられる、というのはどうだろう。もちろん、努力義務だけではなく、国をあげて、生産・調達を全面バックアップする法律・税制・ファイナンスの仕組を用意する。つまり、地域が地域資源をフル活用するよう促すのだ。
そうして創出された富は、可能な限り、地域に還元されなければならない。
たとえばデンマークでは風力発電に地域の出資15%が義務付けられているが、これによって、少なくとも15%分の便益は地域に還元されるのである。同じように、「食」であれ、「水」であれ、「エネルギー」であれ、生産にあたって地域資本を如何に活用するかは重要なポイントであり、ここが自立経済の第一歩だと考えている。
得られた富を、地域でグルグルと循環させることも重要だ。「カネは天下のまわりもの」と言うが、「まわす」ことで波及効果がうまれ、雇用創出につながる。宮崎県都城市の実践は良いお手本になっている。公共事業を地元企業中心に発注することで経済効果は数倍になった。
日本は、年間に「食料」を約8兆円、「エネルギー(石油・石炭・天然ガス)」を約20兆円輸入している。いずれも、国民が額に汗して稼いだ外貨での購入だ。日本人は一生懸命に働いているのに、なぜ豊かさを実感できないのか?…その理由はこんなところにあるのかもしれない。日本列島の資源をフル活用できれば、そのぶん輸入は不要となり、それだけ国民は豊かになるのだ。
地域が、地域資源をじょうずに活かして自立経済を実現する。その努力の積み重ねで、豊かで逞しい「分散自立型の日本列島」ができる。たとえ中央政府が借金で潰れることがあっても、しっかり大地に根をはった地域が「分散自立」している限り、われらが日本は大丈夫なのである。
続・日本の食料は?
2020.10.12
「今年のノーベル平和賞は、国連の世界食糧計画(WFP)に授与される。」
ニュースを聴いて、なるほどと思った。世界の食糧事情は悪化しているし、解決には国際社会の協力が不可欠である。あらためて、国際社会に警鐘を鳴らすためのノーベル平和賞なのだ。
これからの時代、日本の食料事情もさらに厳しくなる。当然、新しい食料政策が必要になろう。
たとえば「気候変動」にどう適応するのか。今年もそうだったが、すでに梅雨は長期化しはじめている。これからは梅雨というより雨季のようになるらしい。西南日本が“亜熱帯”になれば、当然ながらその農業のあり様も変わる。そして、日本列島全体で同様のことがおきる。全国的に気温が上昇するのだから適地適作も変わっていかざるをえない。「気候変動」を見越した食料政策が必要である。
「脱石油」にはどう対応するのか。現代農業は、機械を動かすのも石油。化学肥料も石油。輸送や冷蔵のサプライチェーンも石油に依存する。しかし時代は「脱石油」へと向かっている。このまま石油頼みとはいかぬ。この先、生産から供給までがそっくり変わるのだ。
実は、一滴の石油も使わぬ、太陽光と水だけの食料生産技術が確立されている。宮崎大学・西岡教授の研究成果を見学して、わたしも大いに昂奮した一人だ。このような、人類の未来に希望を与える研究や事業は随所で始まっている。しかし、“全体像”はまだ描ききれていない。
輸入すれば良いじゃないか、と言う人は今でもけっこう多い。
戦後日本は、経済発展を目標にかかげ、我武者羅に効率性を追いかけた。食料は輸入の方が効率的だとされ、国内農業の衰退は見て見ぬふりをされた。その結果が、今日の食料輸入大国ニッポンである。約9兆円の国内生産に対し、輸入は約8兆円。なんと約半分を海外に依存する、イビツで脆弱な国になり果てた。
日本の「国力」はこれから徐々に失われる。輸入すれば良いじゃないか…などと呑気なことは、もう言えないのだ。
ノーベル平和賞にこめられたメッセージをうけとめよう。新しい食料安全保障に舵をきるときが来ていると思う。
「戦戦競競」
2020.10.8
宮澤喜一元総理は「薄氷をふむが如くせよ」と口癖のように言った…と、以前、何かの記事で読んだ。「戦戦兢兢 如臨深淵 如履薄氷(深い淵をのぞくように、薄い氷を歩くように、慎重に謙虚にせよ)」という『詩経』の一節からの引用で、つまり宮澤元総理は、謙抑的な権力運用を心がけておられた、ということだろう。
権力者が力任せにやろうと思えば何事もやれる。けれども為政者に、おそれとつつしみの心がなければ、国民は心服できないのではないか。政治は力だと言われるが、力だけでは永続きはしまい。それは歴史をみれば明らかだ。
保守政治の本質は「寛容」である。「異なる意見にも耳を傾ける度量」と言い換えてもよい。それを保障するのが「自由」なのだと思う。思想信条の「自由」、学問の「自由」、信教の「自由」、表現の「自由」、言論の「自由」、報道の「自由」…。
いま果たして、わたしたちの社会において、これらの「自由」が活き活きとしているか。たとえば政治や行政の現場において。たとえばジャーナリズム、メディア報道において。どうか。
「世界報道の自由度ランキング」で、日本は第66位(2020年)だった。2013年以降ずっと低順位が続いていることを、わたしたちはもっと深刻に受けとめるべきだろう。
先日、海外で勤務する知人から、驚くべきことを聞いた。香港弾圧問題にコメントする日本が国際社会から冷ややかに見られているというのだ。つまり、“目くそ鼻くそ”という意味である。背筋がゾッとする話ではないか。
「米中冷戦」にあらず
2020.8.17
米国ポンペオ国務長官は7月23日、演説で「全体主義イデオロギーの中国を、民主主義陣営で包囲しよう」と呼びかけた。この、あたかも「米中冷戦」が始まったかのような物言いに、わたしは危うさを感じる。
パリ協定から離脱、イラン核合意からも離脱、WHOからも離脱の構えをみせるトランプ政権が、唐突に「新たな同盟を」と呼びかけたところで説得力に欠ける。しかもポンぺオ演説には、議会内にも共和党内にも政権内にも異論があるというし、国際社会においても賛同国はさほど多くない。ポンぺオ演説を額面通りに、というわけにはいかない。
思えば、トランプ政権が誕生した頃は盛んに「貿易戦争」と言った。それがいつしか「ハイテク・安全保障の戦い」と言うようになり、今回のポンぺオ演説では「イデオロギー対立」と言うに至った。
だが、ホントウだろうか。世界はホントウに、全体主義vs民主主義で対立しているか。かつての米ソ冷戦のようにイデオロギーで陣営対立しているのか。そうではなかろう。
米中対立の実態は、あくまでも「覇権争い」である。米国の国益と、中国の国益とのぶつかり合いなのである。両国は激しくせめぎ合うが、利害が一致すればいつでも手を握りうる。
かつての米ソ冷戦では、日本は西側陣営の一員であったし、それは妥当な選択だったと思う。
だが、いまの米中対立は「冷戦」ではなく、したがって日本が「どちらの陣営に立つか」と迫られる話ではない。それは、あくまでも他国の「覇権争い」なのである。対立のあおりを受けることはあっても、日本が主体的にかかわるべき話ではないのだ。
核兵器禁止条約に署名すべし
2020.8.12
8月は、6日の「ヒロシマの日」、9日の「ナガサキの日」に合わせて、テレビでも多くの特集番組が組まれる。実録フィルム映像や証言を聴きながら、あらためて原爆の非道を思わずにはいられない。核兵器は人間に与えられた可動領域を超えている。理屈ぬきに「否」と言うべきである。
3年前、国連で核兵器禁止条約が採択されたが、署名国が50に届かず、未発効のままだ。日本政府は米国の「核の傘」(実際は破れ傘なのだけれども…)の下にあることに遠慮して、禁止条約に署名せずにいる。
だが、そんな次元の話ではないのではないか。世界で唯一の被爆国として、日本には核兵器に「否」という義務があるだろう。日本は(日本政府は、と言うべきか)何かに委縮して、生来の直観や感性・感情に蓋をしている。自らの本心に嘘を言っている。
人間は、日々現実を生きるとは言え、理想を求めてやまぬ生き物である。だからこそ成熟もすれば、進歩もする。大転換の今こそ、わたしたち日本人はもっともっと理想を語り、大風呂敷を広げていいのではないか。わたしの耳には、どこからともなく、「日本人よ、小さくなるな。小さくなるな。」という声が聞こえている。
「核兵器禁止条約」発効まで、あと6か国。日本政府は、ひととして素直になって、核兵器禁止条約に署名すべきだと思う。
「敵基地攻撃能力」の愚
2020.8.11
4日、自民党が「敵基地攻撃能力」の保有を政府に提言した。
そもそも敵基地攻撃が「憲法上許されるか?」「自衛権の範囲か?」については議論のあるところだ。仮に、許容されるとしても、「どのような場合、どのような方法で攻撃できるか?」と具体的に規定することは難しい。
仮に、この論点がクリアできたとしよう。その場合、「軍略上のメリットは何か?デメリットは?」という本質的な考察が必要となる。トータルで考えたらデメリットの方が大きかったということになるかもしれない。仮に、メリット大とされたとしても、さらに、「どれほどの装備、人員が必要か?」「何年かかるか?」「予算は?」が検討されなければならないし、最終的には、「わが国がとるべき方策か否か?」という政治決断と、国民的合意が必要となる。つまり、簡単な話ではないということだ。
わたしは、断乎として反対である。いかに自衛と言い、いかに中朝の脅威がと言おうとも、「敵基地攻撃能力」が周辺国へ向けた軍事的攻撃力であることに変わりはない。相手からすれば首都までも射程に入ったと警戒するのは当然で、軍拡競争のきっかけになりこそすれ抑止力になると安直に考えるべきではない。わが国にとって最大の安全保障とは、アジア諸国に敵意を抱かせない外交を展開し、「日本はなくてはならない国だ」との信頼を得ることのはずだ。
何よりも、「敵基地攻撃能力」を保有した場合、わたしたちの日本はとてつもなく大事なものを失う。それは、「非軍事外交」「平和国家」という戦後日本の“いきざま”である。“いきざま”によって築かれた信頼である。アジアに侵略し、多大の損害と苦痛を与えた挙句に大日本帝国は滅びた。ゆえに戦後日本は、アジア諸国の軍事的脅威とならぬことを決意し、「非軍事外交」「平和国家」を国是に掲げ、国際貢献に汗をかきながら75年を歩んできた。今ここで「攻撃能力」を保有してしまえば、戦後日本の努力は水泡に帰す。
日本の役割は、東アジアにおいて「平和と安定」を創りだすことにある。諸国に、紛争回避メカニズム構築を呼びかけるべき日本が、自ら軍拡競争の罠にはまっては説得力もなにもなかろう。
日本はアジアの国である。アジアにおいて、諸国の信頼を得られずして日本に未来はない。いま安全保障環境が厳しいからこそ、なおいっそう「平和と安定」に汗をかくことだ。これが日本への信頼につながり、ひいては日本を守ることになる。
日本はどう生きるか(その1)~拠って立つところ~
2020.7.22
世界を見わたすと、超大国アメリカが内向きになりプレゼンスを縮小させる一方で、覇権主義の中国がめざましい勢いで台頭している。国力を失いつつある日本にとって、見通しのきかない実にやっかいな時代となった。
日本はどう生きるべきか。その答を出すには、まず、日本がどんな国なのかを見つめ直すことが大事だ。
近代化以降、帝国主義に手を染め軍事力をもって海外に展開し、世界に孤立して破滅するまでの戦前の歴史。それから、「平和国家」を標榜し、軍事力ではなく法律や規則、外交交渉や国際協調をむねとして、自由貿易の恩恵を受けて経済発展を成し遂げ、国際貢献にも尽力してきた戦後の歴史。わずか150年ほどの間に、正反対の二つの生き方を経験した日本が、ここから学んだ事とは何か。
それは、平和と安定なくして国家の繁栄はない、ということではなかったか。この一事を学び取るために、先人のおびただしい血と汗が流されてきた。わたしたちは、この厳然たる歴史を静かに振り返り、その教訓に拠って立ちながら、日本の針路を考えるべきだと思う。
二つの超大国に挟まれた日本。どんな生存戦略を描くべきか。ザックリ言って選択肢は三つあると思う。第一に対米追従。第二に対中連携。第三に自立路線。いずれが日本の進むべき道か。
日本はどう生きるか(その2)~対米追従か~
2020.7.22
米国と一体化して中国の脅威に対抗する。この選択肢は、まさに今の政府・自民党のとるところだ。しかし古今東西を見わたして、主権国家が他国に追従することで生き残った、などという話を聞いたことがない。あるとすれば、それは保護国であり属国と呼ばれるべきものであって、主権国家、独立国家ではあるまい。
わたしたち日本人の意識の中には、米国に守ってもらっている…という考えが相当程度に浸透しているようだが、これは、一方的な思い込みにすぎない。厳しいリアリズムの支配する国際社会において、自国の利益を減じてまで他国のために犠牲を払う国など存在しない。それは米国が、尖閣列島の「領有」について中立を決め込んでいることからも、「核の傘」がほとんど破れ傘であることからも、明らかだ。
外国頼みに狎れると、“アメリカさんの要求は断れない…”などという卑屈なメンタリティに陥る。ハッキリ言って今がそうだ。
今年一月、米国の要求を断れずに、海上自衛隊部隊を中東海域に派遣した。政府は、日本船舶を守るためと説明するが、取って付けた言い訳にすぎない。今こうしている間も、海自艦は中東海域を遊弋しているのだから、いつなんどき、何かをきっかけに、米国とイランの紛争に巻き込まれるかわからない。仮にそうなれば、日本は名実ともに立派な戦争当事国となる。もちろん、米国はそれを望んでいるだろう。
かくして、“米国の要求は断れない…”“仕方がない…”などと言いながら、「平和国家」「非軍事外交」という戦後日本の国是を捨て去って、果てしない対米追従の道を行く日本。気がつけば、キリスト対イスラムの千年抗争に「米国十字軍」として動員されようとしている。わが国はいま、そんな危いところにいる。
しかし、こんなことを国民が望んでいるか。いったい誰が、いかなる責任において、国民を巻き込もうというのか。対米追従路線は、この先行き止まりの袋小路である。日本の進むべき道ではない。
わたしは何も、米国と喧嘩しようと言うのではない。日米関係が重要なればこそ、本当の信頼関係をと言いたいのだ。
トランプ大統領の暴露本で明らかになったように、日米安保条約はすでに歴史的な役割を終えている。それにもかかわらず、体形に合わなくなった洋服に無理に体を合わせようとして、日本はどんどん卑屈になっていく。いったい何のための条約なのか、もう自分でも分らなくなっているようにみえる。
新しい時代に相応しい日米関係を構築するときが来ている。
日本はどう生きるか(その3)~対中連携か~
2020.7.22
それでは中国と連携するか。言うまでもなく、この選択肢もとりえない。
統一と分裂割拠をくりかえすのが中国の歴史だが、その長い歴史のなかで幾たびか、日本は中国との向き合い方に苦悩してきた。いまこそ日本は、この歴史的知見を活かすべきだ。中国の脅威に怯えるあまり、日米同盟で中国封じ込めよ…などと声高に叫ぶような、了見の狭いことでは国を誤る。
香港にみるように、中国はいま、強権的・独裁的な傾向を強めている。一見それは中国の強さのように見えるが、実はもろさの顕れのようにも思える。なぜなら、自由と民主主義をあまりに軽んじているからだ。
ある国家が、たとえば危機に瀕したとする。そのとき、ありったけの叡智を集められるかどうかが一国の命運を左右するだろう。そして、叡智を集められるかどうかは、その国において自由と民主主義が保障されているかどうかにかかっている。強権的・独裁的な国は、一見強そうに見えても実はもろい。
ひとは誰からも管理されず、自らの意思で生きる天賦の権利を有する。自由を希求するのは、ひととして当然のことであり、中国政府がいくら力づくで抑えようとも、香港人の自由への渇望を消し去ることはできない。これはウイグルや、チベットについても同様だ。
日本は今、香港の自由と民主主義を奪った中国政府を、声を大にして非難しなければならない。誰かの自由が奪われるのを見て見ぬふりするならば、いずれ己の自由をも失うことになる。
いわゆる大アジア主義演説(1924年)のなかで孫文は、『今後日本が世界の文化に対して、西洋覇道の番犬となるか、あるいは東洋王道の干城となるかは、日本国民の慎重に考慮すべきことだ』と説いた。しかし日本は聴く耳を持たず、結局のところ、世界で孤立し破滅した。
今あらためて考えてみると、孫文の大アジア主義演説は、日本帝国主義への痛烈な非難であったと同時に、今日の覇権主義中国への鋭い警告のようでもある。
つまり日本は今こそ、「覇権主義による繁栄は永続きしない」という教訓を、真正面から中国に語るべきである。孫文がそうしたように。きっと中国は言うだろう、日本にそんなことを言う資格があるのか、と。それでも日本は、歴史における自らの非をきちんと認め、悔いるべきを悔い、そのうえで言うべきを言えばよい。
日本が、真に自立する国であるならば、つまり本当の自信があるならば、中国と正面から向き合えるはずだ。
日本はどう生きるか(その4)~自立路線~
2020.7.22
日本はどう生きるか。結局、最後の選択肢が残った。つまり日本は、米国と中国の二大スーパーパワーに挟まれながら、しかしそれぞれとの「間合い」をとりつつ、ありとあらゆる外交努力を重ね、国の独立を守る。これ以外にないということだ。
自主防衛なんてホントウにできるのか…という心配の声もあるだろう。けれども自国だけで国防が可能なのは米国くらいのものだ。どの国であれ、軍事力だけでなく外交力、経済力、文化力、国際世論、何よりも自主独立の気概、これら総力をあげて国の独立を守っているではないか。なぜ、はじめから、日本にはできないと考えるのか。
日本に欠けているのは能力ではなく気概である。敗戦後の日本は、主権の一部を放棄し、安全保障を米国に委ねてやってきた。いつの間にか、思考停止に陥り、世界はこうあるべきだ、日本はこうしたいという理念も信念も無くしてしまった。自主独立の気概を失った日本が、これからの激動の世界を生きぬけるとは思えない。
いま必要なのは、いったん立ち止まって、自分自身を見つめ直すことだ。平和と安定の尊さを、日本は身をもって学んだ。ならば、その理念を確固たるものにして、国際社会のなかで、スジの通った主張をし、かつ行動すればよい。「核兵器は廃絶すべし」と堂々と言えばいいし、「中東に自衛隊は出さない」と言って断ればいい。「敵基地攻撃能力」などは愚の骨頂。自らの信念を自らの言葉で語るならば、日本外交はかならずや説得力をもつ。国際社会はしっかりと見ている。
辛かろうが、苦しかろうが、のたうちまわりながらでも、自主独立を守り抜く。いつの時代も変わらぬ原理原則である。わたしたちは、戦争と敗戦のショック状態から脱し、国家として立ち直る時期にきていると思う。
ところで、仲間はいた方がいい。米中の二大ショッピングセンターに挟まれた日本を「鮨屋」にたとえるならば、世界には「焼肉屋」もあれば「ラーメン屋」もある。「カレー屋」も、「パスタ屋」も、「ワインバー」、「ビアホール」だってある。みんなで連携して「商店会」をつくり、「鮨屋」はその一会員として(できれば副会長くらいになって)一生懸命、汗をかくことだ。
日本は、真の独立国と言えないまま、今日まで来てしまった。だが、これからの世界情勢は、半独立国家の生存を許さないだろう。
一国の独立は、民族的熱狂なくしては成し遂げられない。国民の魂が、揺さぶり揺さぶられ共鳴し合うようなエネルギーがなければ、回復できるものではない。まずは、ひとりでも多くの日本人が事実を知ることだ。知ることで魂に火がつき、いったんついた火は消えない。そして必ず燃えひろがる。わたしたちの眼の黒いうちに、かならずやり遂げたい。
日本はどう生きるか(その5)~政治はどうあるべきか~
2020.7.22
新型コロナ・パンデミックの展開次第によっては、バブルに支えられた世界経済はどうなるかわからない。財政ファイナンスの日本が無傷でいられるはずもなく、通貨下落と超高インフレ、大失業に見舞われる可能性もなくはない。巨大地震だってそう遠くないのだ。わたしたちは、これからが国難のオンパレードだと覚悟すべきだ。
みんなで国難をのりこえるには、政治への信頼が欠かせない。これがいちばん大事だと言ってもいい。しかし今、まさにその信頼が失われている。生活苦による不満のマグマが膨らんでいって、ここに政治不信が引火したらどうなるか。歴史は、破滅的なポピュリズムの生まれ得ることを警告している。
政党政治に、信頼を取り戻さなければならない。自民党は、寛容で、度量のある、本来の保守政治に回帰すべきだ。国民の不安を抱きとめながら、野党にも協力をよびかけ、知事や首長などとも連携すればいい。国をあげて、みんなで国難に当たる姿をしめすことが大事だ。
いま政治がなすべきは、戦後政治の総点検、そして大転換だ。外交も、安全保障も、経済政策、食料、エネルギー、通貨、教育、環境、国土政策、住宅都市、社会保障、防災…それぞれの分野において、これまでの諸政策を総点検し、新しい時代にふさわしい目標におきなおす。
日本人はガイアツがないと変われない…と言われるが、たしかに、一度決まったことを変えるのは大の苦手だ。だがこれは、わたしたちの重大な弱点である。
文明史的スケールで転換期を迎えている今、わたしたち日本人は、自らすすんで、おのれの弱点を克服しなければならない。自主自立の気概さえあれば、日本人にはできると信じる。
自ら変革するとき ~脱炭素~
2020.7.2
「新型コロナウイルスは人類にとって最も緊急性の高い脅威だ。しかし、長期にわたる最大の脅威は気候変動問題であることを忘れてはならない。」(国連気候変動枠組条約締結国会議・エスピノサ事務局長)
気候変動に起因する災害、食料、保健衛生、感染症などのリスクは想像していた以上に大きい。人類の生存にかかわるほどに深刻だ。だから世界は気候危機に正面から向き合い、動き出したのだ。とくに欧州は、脱炭素を明確に打ち出し、行動を開始している。
もはや止まることのない世界の流れ。乗れなければ孤立する。日本も迷わず「脱炭素」に本腰をいれるべきだ。そうすれば、高い技術力と文明観をもつ日本人のことだ、必ずや世界をリードし、立派にやっていくだろう。
だが、日本はハラをくくれない。この春も、パリ協定で求められた高い削減目標への改定ができず、国際社会を失望させた。エネルギー基本計画で2030年の電力構成が決まっているので変えられない…というわけだ。しかしこの電力構成、とても現実的な数字だとは思えない。つまり、変えない理由になっていないのだ。
「いったん決まったことは変えられない…」、「クロフネ、ガイアツなしに自ら変革できない…」、これは、わたしたち日本人の弱点である。
この際わたしたちは、脱炭素という大目標にむかって舵をきるべきだ。これは、自ら変革すること、弱点を克服することでもある。
主権国家としての危うさ
2020.6.24
そんなことだろうと思ってはいたが、元側近の「回顧録」でトランプ外交の舞台裏を知らされると、やはりショックを禁じ得ない。今日は、3点だけ触れておきたい。
まず第1点。昨年6月、こともあろうにトランプ大統領は、自身の再選のために、ウイグル人権弾圧問題を“取引”材料に使った。見返りとして、中国の国家主席に「ウイグル人強制収容は正しい、収容所を建設すべきだ」と述べたという。なんたることだ。
ウイグルの民の絶望を思えば、黙っているわけにはいかない。間髪入れずに、トランプ大統領と中国政府の非を鳴らさねばならない。
第2点。北朝鮮ミサイルに関しても、トランプ大統領は「中距離ミサイルはあった方が良い、日本が武器を買うからだ」と述べたとされる。事実ならば、同盟国への許されざる背信である。わが国は断乎として抗議し、日米安保条約の見直しを通告せねばならぬ。条約の前提が崩れたのだから。
そして第3点。在日駐留軍経費のうち、現行1920億円相当の部分を4倍以上の8500億円に増額要求するにあたって、トランプ大統領は「在日米軍をすべて撤退させると言って日本を脅せ」と指示したとされる。これは、わが国に対するこの上ない侮辱であり、聞き捨てならぬ一言である。“売り言葉に買い言葉”としてではなく、ここで真正面から、「撤退していただいて結構です」と返すべきである。思うに、日米安保条約・地位協定はそもそもの歴史的役割を終えつつある。トランプ大統領の発言を、現行条約・協定を見直すきっかけにすればよい。
ましてや、駐留経費の4倍増などという、言われなき要求は、断乎として拒否せねばならぬ。わが国はすでに、法外の“思いやり予算”を含め、毎年8000億円ほどを拠出している。増額どころか、大幅減額が相当である。
この世の中に、“侮辱と屈服の同盟関係”などありえない。わが国は今、主権国家として危ういところにいる。
戦後75年。旧安保から69年、新安保から60年である。すでに日本も、また世界情勢も大きく変化した。いま、日米間の防衛協力のあり方を考え直すときが来ている。
先日、辺野古埋め立て工事において軟弱地盤が判明し、さらに莫大な資金と15年以上の年月の必要が明らかとなった。この際、安保条約・地位協定を大胆に見直すなかで、「辺野古」を中止する選択肢もありうるのではないか。
トランプ大統領の本音は、いまが時代の転換期であることをハッキリと知らしめた。
「自由」を奪う中国を非難する
2020.6.22
香港の「自由」が風前の灯だ。
中国の「香港国家安全維持法」の詳細が明らかになってきた。施行されれば、香港の自由は“合法的”に奪われることになろう。
香港の拒絶意思がハッキリしているにもかかわらず、中国政府はかたくなである。しかし中国政府がどう強弁しようとも、人々の意に反した施政が正当化されることはない。
先月、イギリス・アメリカ・オーストラリア・カナダの英連邦四か国は「香港の自由を脅かすもの」との非難声明を発表した。当然の声明だろうとは思うが、いささかの気持ちの悪さ、違和感もまた禁じえない。なぜなら、もともと香港は、アヘン戦争・南京条約、アロー号事件・北京条約を通じて、英国が清に割譲させたものだからだ。
いま、何より尊重されるべきは、権益や、面子や、歴史的経緯からくる言い分などではない、香港の「自由」である。ひとは、自らの意思で生き、誰からも管理されない、という天賦の権利を有するのだから。
他者の自由を軽んずる者は、いずれ、自らの自由をも脅かされよう。ここに声を大にして、香港の「自由」を踏みにじらんとする中国政府を非難する。
新型コロナ、自由と民主主義
2020.5.8
自国第一に取りつかれたトランプ大統領の米国。対コロナ方針はなお定まらぬように見えるし、WHO批判をくりかえす姿にも世界の指導的立場としての自覚は感じられない。こんな調子では、自由と民主主義のチャンピオンとしての威信に傷がつくのではないか。
かたや、強権を発動し、力づくで感染拡大を抑え込んだ中国。情報隠蔽、都市封鎖、徹底した行動監視などの手法は、自由と民主主義を重視せず、私権の制限に躊躇のない彼の国だからこそ可能だったにちがいない。いまや中国は、医療器材や医薬品で世界を支援してみせるなど、明らかに“コロナ後”を意識している。
グローバル資本主義の帰結として、世界で格差が拡大し、中間層が没落する。それが世界を右傾化させ、ポピュリズムを台頭させた。かくして自由と民主主義が輝きを失いつつあるなかで、パンデミックが発生した。気がかりなのは、自由と民主主義の求心力がさらに失われるのではないか。世界が、強権と独裁への志向を強めるのではないか、ということだ。
わたしたちの日本はどうか。安倍首相は、5月3日(憲法記念日)のタイミングにあわせ、感染症対策と関連づけて、あらためて憲法改正を訴えた。日本国憲法に「緊急事態条項」を書き入れ、非常時の政治に強い権限を与えよ、との主張だ。国家の非常時における法制は準備されて当然だが、国民の自由を制約する事柄を安直に取りあつかって欲しくはない。
そもそも今日の感染拡大は、憲法に「緊急事態条項」が無かったせいではない。三か月も前から、充分な検査と治療体制の必要が叫ばれてきたにもかかわらず、政府はいまだ有効な体制を構築できずにいる。この辺の経緯については今後しっかり検証されなければならないが、いずれにしても、憲法が原因でないことはハッキリしている。自らの拙劣を棚にあげ、この機に乗じて改憲をとは、些か悪乗りが過ぎよう。
やがてコロナは終息する。そのとき、世界はどうなっているだろうか。中国式の強権的・独裁的なあり方をよしとする声が増しているのだろうか。だが仮にそうだとしても、わたしは、日本のすすむべき道はその真逆にあると信ずる。
なぜか。たとえばある国が危機に直面したとする。そのとき、ありったけの叡智を集められるかどうかが国の将来を分けるだろう。そして、叡智を結集できるかどうかは、その国において自由と民主主義が機能しているかどうかで決まる。強権と独裁は結局のところ、もろく、あやうい。
自由と民主主義をより成熟させる。これが日本のすすむ道だ。
日本の食料は?
2020.4.27
コロナ感染が世界規模で拡大するなか、食料の生産・流通・貿易に混乱が生じ、世界はにわかに食料危機の様相を呈している。世界食糧計画(WFP)はじめ国連食糧農業機関(FAO)、世界貿易機関(WTO)、世界保健機関(WHO)も、こぞって懸念を表明した。ここでも、グローバル経済の脆弱性が露呈したかっこうだ。
ただ食料不安はいまに始まったことではない。コロナによる混乱がなくとも、気候変動、水不足、土壌流失、人口増などで世界の食料事情は年々深刻度を増している。この機会に、食料輸入大国ニッポンこそは、おのれの弱点を直視すべきだ。
いざという時を考えるとゾッとする。たとえば「穀物」は国産1000万tに対して輸入は3000万tである。「農地」は、全国450万haでフル生産しても国内需要の4割弱(カロリーベース)しかまかなえない。さらに、「輸入額(油脂等を含む)」は8兆円弱(2018年)だが、日本の国力は衰退傾向なので、いつまで買い続けられるのか保証はない。
いざというとき、最低限どれだけの食料を生産して、いかにして国民の食を守るか。食料安全保障という基本中の基本について、アタマをきりかえて、大きく構想しなおすときだ。
大掛かりな失業対策の必要
2020.4.20
いま、コロナ退治とともに、困窮する国民の救済が急務である。さらに今後、失業者の急増も予想されるが、これは不景気にともなう一時的なものではなく、構造的な大規模の失業となる可能性がある。したがって政府は、時をおかずに、大掛かりな失業対策・雇用創出策を打ち出すべきである。
雇用創出といえば、思い浮かぶのは田中角栄元首相の「日本列島改造論」だ。これは、国土のグランドデザインをダイナミックに描くなかで有効需要を創出し、全国的に雇用を生む、という壮大なプランであった。今回予想される大失業には、「列島改造論」に匹敵するような、大掛かりな構想をもって立ち向かうべきだ。
ところで、この「列島改造論」をもってしても東京一極集中の流れは止められなかった。工業立国をかかげ効率性を追求しつづけるかぎり、日本はこの流れを逆転できないのだろう。
だが、ひょっとしたらコロナ危機が逆転のきっかけをつくるかもしれない。すでに多くの識者が述べておられるように、コロナ危機はこれまでの産業や経済社会のあり方をドラスティックに変えるかもしれない。その場合、「一極集中」から「分散自立」へとベクトルが変わる可能性はある。あの田中角栄ですらなしえなかった大転換があるのなら、ここに大掛かりな失業対策を仕込まなければならない。
ひとは「食料」と「水」と「エネルギー」がなければ生きられない。いつの時代にも、つまり経済恐慌がおきようと、財政が破綻しようと、これらはわたしたちの生存に欠かせない物資である。にもかかわらず、日本は約8兆円分の「食料」と、約20兆円分の鉱物性「エネルギー」を毎年輸入している。まるで生殺与奪の権を外国に委ねているようなものだが、はたして、このさき安定輸入できるのかどうか。
ならば、この際、全国それぞれの地方が、「食料」「水」「エネルギー」を可能な限り自給をめざすべきではないか。地方みずから富を創出し、地域経済をグルグル循環させて乗数効果的に活気づけ、雇用を創出することで全国に何十か所、何百か所もの自立した地域社会ができあがるならば、日本は晴れて、持続可能な、足腰の強い国となることができる。こうして、中長期的な国づくりのグランドデザインを描くならば、そこへ人々が回帰する道筋をも折り込むことができるだろう。
言うまでもなく、失業者にはまず今日、明日の仕事が必要である。たとえば2年程度の任期つきで公務員として受け入れるなど、公的部門の出番である。あるいは洪水予防のための河床浚渫のように、やるべき公共事業はいくらでもあるし、幅広いメニューで雇用を創出することは可能だ。このように、まずは緊急の受け皿を用意し、それがやがて、分散自立型の国づくりの中で、ひろく吸収されていくような段取りを構想するのだ。
補正予算案には、地方自治体が、ホテル借上げや“協力金”などに充てる「地方創生交付金」が1兆円計上されている。わたしは、この「地方創生交付金」について、使途・規模ともに格段に増強し、今後数年度にわたって継続的に予算確保すべきだと考える。
大掛かりな失業対策のため、そしてポストコロナ社会・分散自立型の国づくりのために、その主役となる地方に対して、国は出来得るかぎりの支援をしなければならない。必要とあらば、既成制度の発想をこえて法律を作り、税制を整え、ファイナンスの仕組みを準備すれば良いのだ。ここは日本国にとって、“乾坤一擲の大勝負”かもしれない。
今こそ、イランの声に応えよ
2020.4.16
コロナ感染が深刻なイラン。ラフマニ駐日大使は先月25日、東京都内で会見し、「米国の一方的かつ非人道的な制裁で、必要な医療機器や医薬品の調達に大きな支障を来している」と窮状を訴えた。
昨年6月、米国とイランの双方に請われ、一度は、両者周旋に汗をかいた日本だ。ならば再度、両国の間に入るのは義理である。米国の制裁見直しを促すなり、イランの医療を支援するなり、やり方はいろいろあるはずだ。
いま、世界はパンデミックの渦中にあり、先の見えない窮地に立つ。ワクチンや特効薬の開発をはじめ、世界の結束した協力が欠かせない場面だ。中国批判の道具立てのつもりか、WHOへの拠出金を渋るトランプ大統領はあいかわらずで、まったくもって困ったものだ。大ダメージを受けつつある世界経済は、いずれ、各国協力のもとに復興に向かわねばならないが、そんなとき、自国一国さえ良ければ…ではうまくいくはずがなかろう。
伝染病だけではない。世界には核、温暖化、食料、貧困…と、国際社会の協力なくして解決できぬ難題があふれている。いまや、世界は一蓮托生である。国際政治の難しさは厳然としてあるにせよ、私たちは、どこかのタイミングで一段高みにのぼらねばならない。国際社会全体での協調が、何も特別なことではなく、日常茶飯事であり、空気のように自然なことなのだと思える世界にしなければならない。世界が共通の厄災に襲われている今こそ、一歩も二歩も踏み出すときだ。
分断、対立、不寛容な世界ではいけない。より良い世界にするために、日本は日本なりに力を尽くすことができる。それは、理念を掲げ、スジの通った主張をし、行動することだ。そのような日本のなす主張は、必ずや説得力をもつ。まずは、イランの悲痛な声に耳を傾け、これに応えて、具体的な行動をとることだ。弱い者イジメはよせ!と割って入る義侠心のような、人として素直で、当たり前の行いができるかどうか。ここが日本の第一歩だと思う。
アタマを有事モードにきりかえよ
2020.4.12
有事である。パンデミックに打ち勝つため、アタマを平時モードから有事モードにきりかえて、緊急かつ大胆に迎撃体制を敷かねばならない。まず医療、そして雇用、金融、経済と、あらゆる分野において。連日の悲惨なニュース報道もあって、国民はすでに事態を理解し、スタンバイしている。なのにひとり政府だけが、いまだに「平時」のアタマのままだ。
肝心の医療体制だが、刻一刻と勢力を増す「敵」(コロナ)への迎撃態勢がいまだ組めずにいる。政府は、医療機関にはコロナ診療ごとに診療報酬を加算すると言うが、人工呼吸器どころかマスク・防護服すら不足するなかで、感染リスクや経営不安とギリギリ向き合っているのが医療現場の実情だ。診療報酬でコロナに対処せよとは、民生費予算で戦争を戦えと言うようなもので、とても政府の本気度が感じられない。要するに、政府はいまだ平時アタマなのだ。
不可解なのは、いつまでたっても検査体制が整わないことである。「敵」がどこにいるのか分からぬままでは戦いようがない。もたもたするうちに、医療機関など大切な社会インフラが次々と「敵」の攻撃をうけて動けなくなっていく。政府は、どれほど指摘されても限定的な検査姿勢を崩そうとしないのだが、こうして検査が行われない中、静かなる感染は拡がりつづけ、新たな重症患者を生んでいる。これは、いったいどういうことか。
感染拡大を止めるため、外出自粛・休業要請を呼びかけるのは当然である。しかし、食べるために休業したくても休業できない国民への手当もまた当然だろう。見ぬふりとまでは言わないが、国民の不安を和らげようともせず、ただ休業要請をする非情さに、平時アタマの限界を痛感せずにはいられない。いま、困窮し不安を覚える国民に手を差し伸べることは政府の仕事なのだ。財政はこういう時にこそ、糸目をつけずに“大胆に”出動すべきものである。国民のための財政、国民あっての財政であり、国民さえ元気ならば国は滅ばぬ。
ここは国家の一大事。政治の大目的は国民を守ることにある。政府はアタマを有事モードにきりかえて、既成の法律や制度を超えて、発想し、行動すべし。この際、思い切ってやればやるほど良い。戦力の逐次投入は必敗である。必要なら断乎たる手を打て。それが有事のリーダーシップではないか。
“有事”の医療体制を整えよ
2020.3.25
どこかの大統領が「ワタシハ戦時ノ大統領ダ」と言ったように、いま世界でおきているのはまさに有事、新型コロナウィルスとの戦いである。わが国が最優先すべきは国民の“命”を守ることであり、ウィルスとの戦いに打ち勝つことだ。
世界に冠たる日本医療ではあるが、現態勢では有事に対処できない。発熱外来や検査所、患者の仕分け、治療の役割分担など、地域の医療機関同士での連携・協力体制を整えること。あわせて、医療従事者、機器・器材・医薬品、医療施設を確保することは急務である。急ぎ、有事対応のフォーメーションを組みあげねばならない。
日本の皆医療は診療報酬で賄われているが、有事においては、どうしても別段の財源が必要となる。この際、新型コロナ対策として相当規模の予算を確保し、万全の態勢で臨むべきだ。
政府は、近く、大型補正予算を組む。当然のことながら、国民の雇用を守ることは重要だし、急ブレーキのかかった事業活動を守ることもまた重要である。しかし最優先すべきは、刻一刻と勢力を増す“敵”を迎え撃つことだ。
“乾坤一擲”の財政出動
2020.3.12
高橋是清を尊敬している。「高橋財政」といえば、積極財政の代名詞のごとく言われたりするが、わたしの理解するところ、ときの経済状況に応じて財政出動したり緊縮に転じたりの、柔軟かつ大胆な財政運営こそが「高橋財政」である。高橋は、財政の手綱を締めるべき場面では、迷わずひるまず手綱を引いた。2・26事件で非命に斃れたのはそのせいだったと思う。
ところで、財政政策を機動的に発動するには、健全財政、つまり財政に余力がなければならない。現在の、借金に依存しきったわが国財政に、その余力は残されてはいない。相撲にたとえるならば、徳俵に足がかかってしまった状態だ。あとは捨て身のウッチャリしか手がない。
新型コロナショックが全世界の経済に急ブレーキをかけている。国民生活も、日本経済も、そして世界経済も危い。もともと世界的にバブルが膨らんでいたところに、景気後退の波がヒタヒタと寄せ始めた、そこにコロナショックが起きたのだから、事はただではすまないだろう。
政府は躊躇なく、日本経済と国民の雇用をまもるために最善を尽くすべきだ。財政に余力は無いが、もはや、やむをえない。ハラを決めて、大胆に財政出動すべきだと思う。
足が震えるほど窮まっていることを自覚した上で、わたしはあえて、“乾坤一擲の大勝負”を提案したい。コロナ危機対応にとどまらず、さらに一歩ふみこんで、日本の未来への投資に全力を注ぐのだ。わたしは、「地域経済の自立」「地域共同体の再生」「少子化対策」こそがその急所であり、ここに的を絞って、相当規模の財政資源を投入すべきだと考えている。戦力の逐次投入はしない。“乾坤一擲”のウッチャリの一手である。
これからの日米関係(その1)~未来を展望するとき~
2020.2.22
米国のトランプ大統領は、就任前から今日にいたるまで、「日米安保条約は不公平」「日本は防衛負担を増やせ」「在日駐留軍経費の負担を増額せよ」などの発言を繰りかえしている。米政府高官も日本政府に対して同旨の発言を重ねているので、これは、「米軍再編成」など彼の国の世界戦略にもとづいた主張と受けとめなければならない。
「不公平」との認識には大いに反論のあるところだが、あえて、ここでは触れない。重要なことは、二国間条約の当事者の一方が、明示的に不満を表明していることだ。これは、日本国の安倍首相が安保条約六十周年の式典で、「六十年と言わず百年、いや不滅の柱として…これからも…」とたからかに謳いあげたのとは対照的である。
ちなみに、かつて「戦後レジームからの脱却」を標榜した安倍首相による手ばなしの安保礼賛には、戸惑いを覚える。少なくとも、おいすがるかの礼賛コメントは、日本国の自尊心をひどく傷つけるものに思われるし、わが国がなにか弱音を吐露したかに映る危うさがある。国をあずかる政治家の発言として、いささか軽かったのではないか。
いずれにしても、条約を締結する当事者の双方でこれだけ認識が異っている現実は、すでに現行条約体制が、今という時代をとらえきれなくなっていることを示している。
考えてみれば、永遠につづく条約関係などこの世に存在しない。まして1951年の第一次安保から今日まで69年も経過し、世界情勢も、それぞれの国力も、考え方も、当時とはずいぶん変わってきている。われわれが、ここでいったん立ち止まり、あらためて未来を展望するのは当然のことだ。
これからの日米関係(その2)~日米安保条約~
2020.2.22
日米安全保障条約のこれまでをザックリと振り返ってみたい。まず、敗戦そして占領された時代。わが国は、日本の完全非武装をめざすマッカーサーによって、日本国憲法「9条Ⅱ項」(戦力不保持・交戦権否認)を押し付けられた。米国内にもさまざま意見があったようだが結局のところ、「9条Ⅱ項」によって生じる空白を埋めるものとして「日米安保条約」が締結される。つまり、「9条Ⅱ項」と「日米安保条約」はセット、一対のものとしてこの世に生を受けた。
「吉田ドクトリン」、つまり、敗戦で弱りきったわが国が安全保障を米国にゆだねた判断は、当時の状況からすれば、やむをえなかったものと思う。ただ問題は、主権回復後もこの形が変わらず継続され、60年安保をへて、令和2年の今日にまでいたっていること。そして、その実態が、共産勢力からの日本防衛というより、米国が日本列島を勝手自由に軍事利用するためのもの、となっていることである。事実上の占領状態が続いているということだ。この、世界に類例をみない異例の現状について、わたしたちは立ち止まり、点検すべきなのである。
米ソ冷戦が終結して、第二次世界大戦後の世界秩序はガラリと変わった。これによって、それまでの「日米安保条約」の存在意義は消滅した。日本もすでに、かつての敗戦国ではない。本来ならば、ここで憲法改正つまり「9条Ⅱ項」を削除し、かつ、「日米安保条約」を冷戦後世界に相応しいものに改定すべきであった。
だが、そうはならなかった。なぜか。米国が、優れた立地の日本列島を自由使用できる特権を手放したくなかったのは言うまでもないが、しかしそれ以上に、われわれ自身がなんら行動をおこさなかったことがいけなかった。経済的繁栄に安住し、自主独立の気概を失い、思考停止し、事実上の占領から脱出するチャンスを逸したのはわれわれ日本人自身の失態である。痛恨の極みであった。
冷戦終結からさらに三十年が経過する間に、「日米安保条約」はまったく異なるものへと変質する。これは重大な問題をはらむ変更であったと同時に、変更の手続きにも重大な瑕疵があった。両首脳間あるいは2プラス2という国民不在の場で決定された、つまり、民主国家のプロセスを経ずに決定されたことである。
1996年の「日米安全保障共同宣言」、1997年の「新日米防衛協力の指針」、2005年の「日米同盟の未来のための変革と団結」と、いずれも、実態として、現行条約の規定を大きく踏み外したものであるにもかかわらず、国会の承認を受けてはいない。国家民族の命運を左右する重大事を、ときの政府が合意し、その結果として、日本国民はこれに拘束されるに至ったのである。
かくして、「日米安保条約」は、いまや、民主国家のコントロールの外で自由自在にふるまうモンスターとなった。このモンスターに引きずられ、果てしない米国追従の道を行く日本。しかし、その行き着く先はいったい何処であるか。いったい誰が、いかなる責任において、日本の未来を、かわいい子孫を巻き込もうというのか。空恐ろしさに慄くばかりだ。
これからの日米関係(その3)~海上自衛隊派遣~
2020.2.22
日本国と日本国民を守るための自衛隊を、今回なぜ、中東に派遣するのか。関連船舶と石油を守るためと政府は言うが、後付けの理由に過ぎない。日本船舶はそのような危険にさらされてはいないし、船主組合からも要請はない。ズバリ、〝米国の要求を断われないから〟。それ以外に考えられない。
「日米同盟の未来のための変革と団結」(2005年)では、日米協力の行動範囲が極東から全世界に広げられた。しかも日本はここで、「日米共通の戦略」にもとづき「国際的活動に協力する」ことを合意している。
今回の海上自衛隊部隊の中東派遣は、まさに、この「国際的活動に協力する」一環なのであろう。民主国家としての手続きを踏まぬまま外国と取り決めをし、〝約束した以上は断れません〟とばかりに自衛隊を出す。そういう図柄なのである。とても尋常な姿とは思えない。
これからの日米関係(その4)~歴史の教訓~
2020.2.22
わたしたちは、今こそ立ち止まって、歴史を振り返るべきだ。
わが国は、近代化以降、対外関係を決するに軍事力をもって臨んだ。その結果として国際社会で孤立し、ついには破滅した。これは歴史の事実である。この反省にたてばこそ、戦後日本は『外国の紛争に軍事力をもって介入しない』ことを国是として誓い、国際社会で生きてきた。この外交姿勢は、決して間違ってはいない。
しかし、今回の中東派遣は、アメリカとイランの『紛争』に『軍事力で介入』するものであり、したがって戦後日本の国是の転換にほかならない。〝そんなつもりはありません〟と言おうが言うまいが、国是の転換なのである。
しかも、‶米国の戦争〟に巻き込まれる可能性がある。いや、むしろ米国はそれを心の中で望んでいるのかもしれない、そう考えるのが自然ではないか。だが日本国民の、いったい誰にその覚悟があるだろうか。誰がそんなことを望んでいるか。
そもそも憲法は、今回のような自衛隊派遣を許してはいない。防衛省設置法の「調査・研究」の文言を根拠に、自衛隊を中東に出せるのなら、もはや歯止めなど無いに等しい。すべては、法治国家であり民主国家であるはずの日本国の、コントロールの外にあるようなものではないか。わが国は今、おびただしい犠牲のうえに手に入れた教訓をみずから踏みにじり、道を誤ろうとしているのではないか。
これからの日米関係(その5)~提言~
2020.2.22
「日米安全保障条約」は、すでに今という時代に合わなくなっている。われわれは、これからの日米協力のありかたを真剣に考え、かつ協議を開始する時機に来ている。
不平等な地位協定があたえた特権にあぐらをかき、駐留経費の増額を当然のごとく要求する米国。かたや、〝アメリカに守られている〟と一方的に思い込み、「核の傘」が破れ傘であることにうすうす気づきながら、自分の足で立とうとしない日本。これが健常な関係といえようか。この不健全でグロテスクな二国間関係の原因が、惰性にながれた「日米安保条約」体制にあるのならば、これをゼロベースで見直すのはあたりまえのことだ。
ここからは、わたしの提言である。
いまこそ、本来の憲法改正を行うべきである。「9条Ⅱ項」を削除し、あわせて76条Ⅱ項(特別裁判所の禁止)をも改正して軍事法廷を設置可とする。独立国家にふさわしく自衛隊を国軍として扱う。しかし同時に、わが国は、歴史的教訓を決して無にはしない。『外国の紛争に軍事力をもって介入しない』との戦後日本の国是を貫くのだ。9条Ⅰ項「…国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」の文言そのままに。
「9条Ⅱ項」と「日米安保条約」はその誕生からしてセットであった。したがって、「9条Ⅱ項」を削除すれば「日米安保条約」の役目もまた終わることとなる。日米両政府の合意のもとで、たとえば十年の期間をへて条約を解消することとし、引き続き、東アジアの安全保障について、どのような日米協力ができるのかを模索する。その上で、時代の要請に応じた、新たな日米条約を締結すればよい。
在日米軍基地は、たとえば2045年(敗戦後100年)までの完全撤収を合意し、時間をかけて徐々に実行すればよかろう。主権国家ならば、外国軍隊の国内駐留など許してはならない。
言うまでもないことだが、自国防衛の責任は自国にある。自主防衛体制を整えることは主権国家として当然のことだ。自主独立の気概をもって、①「9条Ⅱ項」を削除し、②「日米安保条約」の終了を日米で合意し、③自主防衛体制を整備し、④新たな日米防衛協力体制を構築し、⑤北東アジアに米国を含む多国間協議の場を設ける。この①~⑤を一連のパッケージと考えて実行する。すなわち、独立国家としての姿を取り戻すのだ。
昭和20年、敗戦に際して、米内光政海相が天皇陛下に拝謁し、「私どもはこのたびの敗戦に大きな責任を感じております。日本の再興には五十年はかかるかもしれません。」と申し上げたのに対し、陛下は「五十年では無理だと思う。おそらく三百年はかかるであろう。」と仰せられたという。
今年、戦後75年を迎える。分かれ道に立ついま、自主独立の気概を振るって、正気を取り戻したい。トランプ大統領の不満表明は、絶好のチャンスである。
86万4千人
2020.2.12
昨年生まれた赤ちゃんは86万4千人。“団塊の世代”当時の三分の一以下となった。いま大事なことは、少子化対策の具体的な手を打つことではないか。私案のひとつを紹介したい。
産婦人科医から聞いて驚いたのだが、人工妊娠中絶は年間に100万件もあり2割(20万人以上か)は第三子だという。家庭があるのに諦めるのは経済的理由によるところが大きいのではないか。ならば、ここをターゲットにした一手が打てないか。
私案は、中・低所得世帯(ここでは年間収入所得500万円以下を想定した)を対象に15歳未満の子供に応じて給付付き税額控除を行う、というものだ。たとえば、第一子に対して月2万円の年24万円、第二子は4万円の48万円、第三子以降は8万円の96万円の支出を考える。子供3人の世帯なら月14万円・年168万円の税額控除または給付金となる。約1.8兆円が必要となるが、既存の児童手当と配偶者控除を廃止することで相当額を確保できる。増税や借金をせずとも、現行施策を組み換えることでこれだけのことができるということだ。もちろん本案は考え方を示したもので鍛練すべき点は多いと思うが、“子をもちたい人がもちたいだけもてる”ための一提案だ。
国の独立
2020.2.1
日米安保60年ということで、首相が、60年と言わず100年いや不滅の柱としてこれからも…と高らかに謳いあげる姿に絶句した。ふと「戦後レジームからの脱却」という言葉が頭に浮かんだが、何を言っても虚しいばかりだ。
昭和20年、敗戦にあたり米内海相が天皇陛下に拝謁し、「私たちは大きな責任を感じております。日本の再興には五十年はかかるかもしれません。」と申しあげたのに対し、陛下は「五十年では難しいと思う。おそらく三百年はかかるであろう。」と仰せられた。
今年は戦後七十五年。みちのりの、まだまだ遠いことを思わずにはいられない。
財政規律はどこへ行った
2020.1.24
通常国会が召集された。これから、“大盤振る舞い”の元年度補正案そして二年度当初案と、予算審議が始まる。審議においては財政規律のゆるみこそ論点とされるべきだ。
先週、内閣府の中長期試算が公表された。これをみると、日本財政がいかに追い詰められているか、よくわかる。試算によれば、2025年PB(プライマリーバランス)は8.2兆円の赤字と見込まれ、同年PB黒字化の目標達成は相当に厳しい。
わがくに財政はダントツの世界最悪である。日本は言わば、借金で身の丈以上の生活を続けているようなものだが、「これからも続けます」ではマーケットの信認を得られようはずがない。このままでは財政は破綻する。結果、ヒドい目にあうのは国民と将来世代である。
こんなふうに言うと、よく「破綻、破綻と言うがいっこうに破綻しないじゃないか」「オオカミ少年」などと非難されたりする。だがそれは、死に至る病だと忠告する者に対して、「まだ死なないじゃないか」と反駁するようなものだ。とくに最近の「財政赤字はいくらあっても大丈夫」との説には驚く。世の中に打出の小槌など無い。どう理屈をならべようと、借金漬けの財政は続きようがないのだ。
“一国二制度による統一”の行方
2020.1.22
11日、台湾総統選挙で、蔡英文氏が堂々たる再選を果たした。
民主制とは、言うならば「自己決定(誰からも管理されないこと、監視カメラからも)」のシステムである。台湾は、「自己決定」を保障する総統選挙において、「自己決定」を是とする蔡氏を選択した。かくして中国の“一国二制度による統一”は、とことん拒否されたかっこうだ。
となれば、このさき中国はどうでるのだろうか。「武器の使用は放棄せず、あらゆる必要な措置をとる選択肢を残す」(習近平氏)との言葉通り、武力で台湾の「自己決定」を踏みにじるつもりだろうか。同じく「自己決定」の統治原理を支持するわたしたちは、ことの行方を注視したい。
国を誤ることなかれ
2020.1.14
1月10日、河野防衛相は、海上自衛隊部隊の中東派遣を命じた。しかし、である。日本国と日本国民を守るための自衛隊を、なぜ中東に出すのか。その理由がみあたらない。日本船舶と石油を守るためとの声もあるが、後付けにすぎない。しかも、国際世論があるわけでもなく、明確な法的根拠もなく、国会論戦を経たわけでもない。これまでに例のない、実にイレギュラーな海外派遣なのである。
動機は“米国の要求を断われなかった”こと、以外に考えられない。政府は自らの意志というより、「日米同盟」という言葉に自ら縛られた挙句に派遣を決めた。これが実態であろう。
派遣に至るプロセスを見ても、独立国家としての矜持が感じられない。三点、指摘する。まず、外交。“有志連合ではなく日本独自の派遣”だとして、米国とイランの双方に配慮したつもりだろうが、ご都合主義が世界で通用するとは思えない。米国の要求にもとづく、米国側に立った派遣であることは、イランも世界もとうに見抜いている。実際、海自部隊は米軍と「緊密に連携」する。いざ戦争になり、米軍が在日基地から出撃するとすれば、日本はもう立派な戦争当事国である。
次に、自衛隊の運用。防衛省設置法を根拠とした海外派遣は例がなく、これが新たな先例となろう。今後、本法にもとづく調査・研究と言えば何でも通る、つまり歯止めがなくなるおそれはある。さらに、基本的に防衛大臣の決定・責任で海外派遣できることになろうから、それだけ国会のチェックから遠くなる。
三つめは、説明責任。これほどの重大事を決めるのに、わざわざ国会閉会中をえらんでの閣議決定(12.27)であり、発令(1.10)であった。政府には国民を説得するだけの自信がなかった。そう思われても仕方ない。
日本は独立国家として、自信をもって自国の原理原則を貫くべきだった。わが国はいい加減、「米国の要求だから仕方がない」というメンタリティからぬけだすべきだ。「仕方がない」「仕方がない」と言っているうちに、日本は“米国の戦争”にまきこまれる。それを国民は望んでいるか。いったい誰にその覚悟があるというのか。
戦後日本は、「非軍事外交」つまり、他国の紛争に軍事力で介入しないことを国是としてきたではないか。それは日本が、わずか百五十年の間に、「軍事力外交」「非軍事外交」のふたとおりの生き方を経験した結果、他のどの国よりも「非軍事外交」の必要性、有効性を骨身にしみて知ったからではないのか。「非軍事外交」は、そんな日本だからこそアドバンテージとなるものであり、みちゆき日本外交の“切り札”ともなりうるものだ。
遠く中東の紛争に海自部隊を出すことは、これまでの日本の歩みを無にする愚行である。おびただしい犠牲の上に手にしたアドバンテージを、いとも簡単に捨て去ることと同じである。国家としてのこの“変節”が、米国への依存心あるいは属国根性から来るものだとすれば、こんな悲しいことはない。国のために戦って散った無数の先人にあわせる顔などない。わたしたち日本は、ここでいったん立ち止まり、来し方を振りかえり、行く末に眼をこらしてみるべきである。米国追従路線は、この先行き止まりの袋小路になっている。
「日米同盟」と言うならば、米国を諌めよ
2020.1.5
2日、米軍はイラク領内において、イランのスレイマニ司令官をミサイル攻撃で殺害した。米国によるこの蛮行は、厳に非難されるべきである。米大統領は殺られるまえに殺ってやったと胸を張るが、これが許されるのなら国際社会は無法地帯だ。実際、今後どのように事態が拡大していくのか予想もつかない。
「日米同盟」と言うのであれば、ここで日本は米国を諌め、率直に意見を言うべきであろう。殺害をきっかけに中東全域を巻き込んだ戦争に発展するかもしれぬ。その際、在日米軍が日本から出撃するなら、自動的に日本も交戦国となる。しかも、その時すでに海上自衛艦を中東に遊弋させ、米軍とは「緊密に連携」(2019.10.18菅官房長官)しているのだろうから、やっぱり日本は立派な交戦国というほかない。その覚悟があって「日米同盟」と言っているのか、ということだ。
米国に言うべきことは言わねばならぬ。米国の戦争につきあうつもりのないことも予め言っておかねばならぬ。日米地位協定とその運用についても問題提起が必要だ。それが言えぬなら、「同盟」などという言葉を使ってはならぬ。2005年の「日米同盟の未来のための変革と団結」合意は白紙に戻すほかない。
日本の「国是」が変更せられた日
2019.12.27
イラン・イラク戦争の1987年、米国からの要請をうけて、日本政府がペルシア湾への自衛艦派遣に踏み切ろうとしたことがあった。しかし、当時の後藤田正晴官房長官が、「戦争になりますよ。その覚悟はあるんですか。」と猛反対し、ついに中曽根首相もこれを聴き入れ、派遣を断念した。わずか30年ほど前の話である。
本日2019年12月27日、日本政府は、中東海域への自衛艦派遣を閣議決定した。結局のところ、“米国の要求を断われない日本”を露呈したかっこうだ。しかも、国連決議もなく、特別立法もなく、国会論戦もなく、安倍内閣の胸ひとつで海外派遣を決めたのだ。“アメリカに要求されれば閣議決定だけで自衛隊を出す”、その立派な先例ができたことになる。
近代化以降わが国は、対外関係を軍事力で解決しようとして国際社会で孤立し、ついに破滅した。この反省にたてばこそ、戦後日本は「他国の紛争に軍事力をもって介入しない」との原則を貫き、「平和国家」「非軍事外交」を国是としてきたのである。
だが、この国是はアッサリと捨て去られた。戦後日本の外交理念は根本から変更せられたのだ。もはや歯止めは無くなったと考えねばならぬ。後世「アレが日本の分かれ道であった」とならぬよう、わたしたち日本国民は今ここで立ち止まり、熟慮すべきである。
気候クライシスにどう向き合うか
2019.12.19
温室効果ガスによる地球温暖化が、今日の気候クライシスをもたらしている。しかも、このまま温暖化が進行すれば、地球環境は人類の生存すら脅かすに至る。このことは、世界でおきている諸現象や科学的分析からして、もはや否定のしようがない。グレタ・トゥーンベリさんが言うように「温暖化は緊急の対応を要する問題」なのだ。
COP25では、日本は温暖化対策にうしろ向きの国、と非難された。わたしは、かならずしも日本がそうだとは思わない。だが、世界から「うしろ向き」と見られるのは危険だ。世界では企業活動においても、ここにきて急激に、環境意識の有無がその企業の運命を左右するまでになった。今後さらにその動きは加速するだろう。人類の未来が危惧されるなかで、企業であれ、国家であれ、「うしろ向き」とみなされるのは倫理性が疑われるのと同じであり、したがって致命的ダメージともなりかねない。
ここで日本は、国をあげて気候クライシスに向き合うことを決意し、世界にむけて強いメッセージを発すべきだ。脱炭素への行動計画も示さなければならない。本来、文明観や技術力の高さからして、日本こそが問題解決の牽引者としてふさわしい。わたしたちは、この、時代の大転換期にあたって、ハラを決めてかかるべきである。
政府の動きが遅いのなら、まず国会がなんらかの危機感を表明すべきではないか。この問題意識のもとに本日、国会における運動がスタートした(※)。もはや、一刻の猶予もゆるされないと思う。
(※)19日、国会内において、COP25後のわが国が気候クライシスにどう向き合うかを考える主旨で、超党派議員連盟設立に向けた発起人会が開催された。
アベノミクスは”時間切れ”
2019.12.10
政府は5日、事業規模26兆円の経済対策を決めた。財政支出は国・地方あわせて13兆円という大規模なものだ。対策では「経済の下振れリスク」が強く意識されており、多額の財政出動も“背に腹はかえられない”との文脈からであろう。しかし、災害対策はわかるにしても、その他緊急性、必要性につき気になるところもあり、財政規律がゆるんでいる印象はぬぐえない。わがくに財政が、世界のマーケットから信認を得られるか、緊張感ある財政運営がいっそう求められる。
今ここで大事なことは、日本政府が、財政再建目標つまり「2025年基礎的財政収支黒字化」をかならず達成するとの強い意思を示すことだ。「また今回も先送り…」などということにならぬよう、ここであらためて目標達成へのシナリオを示すべきである。
ところで、アベノミクスとは、第一矢「金融政策」と第二矢「財政政策」とで“時間稼ぎ”するあいだに第三矢「構造改革」を断行して潜在成長力を高める、というものであった。しかし始めてからすでに7年、いまでは「金融政策」は副作用が大きくなり過ぎ、「財政政策」は財政悪化がすすみ発動余地はない。もはや、「金融政策」「財政政策」のさらなる発動は無理である。つまり、アベノミクスは“時間切れ”となっているのであり、政府はこの現実を直視すべきだ。
今後、政府の言う「経済の下振れ」は避けられないと思われる。そのときに、わたしがもっとも心配なのは、政府が日銀にさらなる緩和を求め、日銀がそれに応じてしまうことである。仮に、国債買入量を再び増大させた場合、国債の流動性が一段と低下し、危機に直結、命取りになってしまうことを恐れる。もはや、アベノミクスのアクセルを噴かすのは危険なのである。
中村哲氏に哀悼の誠を捧ぐ
2019.12.5
昨日、中村哲氏が襲撃され亡くなった。訃報に言葉もない。氏は35年前にパキスタンで医療活動をはじめ、その後アフガニスタンにも活動をひろげて井戸や農業用水路の整備に力を尽くした。テレビ画面でしか存じ上げないが、「医療ではひとびとの飢えや渇きまでは治せない」「食えないから戦争に狩りだされる、食えるような農村にすることが大事」「困ってる人に力を貸したいと思うのは当然のこと」と訥々と語るお姿が目に焼き付いている。世の中にはこんな立派な方がいらっしゃるのか、と思ったものだ。
こころから哀悼の誠をささげます。やすらかにお眠りください。
香港と、民主政と、日本と
2019.11.25
香港の区会選挙で「民主派」が圧勝した。民主化を求める民意が明確に示されたかっこうだ。条例問題に始まる騒動の先行きはなお不透明だが、人権にかかわることでもあり国際社会はしっかりと見ておかなければならない。
一連の報道に接しながら、香港の人々とくに若者たちの必死の思いに同情、共感している。民主主義の本質は「自己決定」「誰からも管理されないこと」であり、これを希求するのは人として当然のことだ。今後、かれらの民主化への渇望が止むことはあるまい。中国政府のめざす一国二制度がどこまで現実的なのか、今後どのように推移するのか、注視していきたい。台湾も固唾をのんで事態を見つめているだろう。もちろん、日本にとっても他人事ではない。
ところで、わたしたち日本の民主政はどうか。言論NPOの世論調査によると、「政治家・政党を信頼する」との回答はわずか2割。ここ数年の投票率低下は著しいし、統一地方選挙では立候補者不足による無投票も全国に散見された。いま、日本の民主政は空回りしはじめているのではないか。
ポピュリズムも、決して海の向こうの話ではない。政府の財政運営などは、その最たるものだろう。財政破綻を回避するには、社会保障の「給付」を減らし「負担」を増やすしかない。にもかかわらず政府が、国民の反発を恐れてか、破綻回避に本腰を入れない。これは立派なポピュリズムである。
わたしたちは、「自由」の中核である自己決定のシステム、つまり民主政を、上手に使いこなせているだろうか。いま、世界は激動期を迎えている。当然日本も、難しい時代に向き合っている。これからの主役たる若者たちには、何としても民主政を上手に運転していってほしい。今のうちから、若者世代の本格的な政治参入を促したい。そのための思い切った手立てが必要だと思う。
地位協定を改める責任
2019.11.11
3日公表の在日米軍報告書はショッキングだ。パイロットが薬物を常習する、ふざけながら訓練飛行を繰りかえす、日本政府へ事故報告しない、など数々の規律違反、軍紀の乱れがあるという。つづく6日には、青森県で米軍機から模擬弾が落下したが、いつものごとく、日本の警察はこれを接収し調査することすらできない。日本にいながら日本の法律に服すことなく、特権を与えられた在日米軍。あぐらをかいた振る舞いには、怒りを通り越して寒気を感じる。
なぜ、こんな不健全でグロテスクな事態がつづくのか。それはズバリ、日米地位協定とその運用に問題があるからだ。「互恵性の原則」すら適用されず、米国に一方的な特権を認めた本協定は、刑事裁判権・基地管理権・環境権いずれにおいても、世界に例をみぬほど不平等だ。これを正しい姿に改めなければならない。
戦争にやぶれ占領下におかれたわが国は、昭和27年4月28日サンフランシスコ講和条約の発効とともに主権を回復するはずであった。しかし現実には、同じタイミングで結ばれた日米安全保障条約と日米行政協定(今の地位協定)によって、事実上いまも、屈辱的な被占領状態にある。日本の主権は、いまなお損なわれたままである。
同じく敗戦国のドイツのように、本来であればわが国も、冷戦終結後のタイミングで在日米軍を縮小させ、地位協定を改定すべきであった。その機を逸したのはいかにも残念だが、しかし、われわれ世代の眼の黒いうちに、なんとしてもやり遂げねばならぬ。
日米関係が極めて重要なればこそ、地位協定は改定されなければならぬ。多くの国々と地位協定を結び、世界中に軍を展開している米国が、この道理を理解できないはずがない。
日系二世のダニエル・イノウエ上院議員(故人)は生前、「アメリカという国は、こちらが本気になって本音を語れば、耳を傾ける度量をもっている」と言い残した。主権国家として、米国と正面から向き合うことだ。駆け引きは不要である。
首里城が象徴するもの
2019.11.6
焼失した首里城を視察した。じかに惨状をみて、地元の方々の声を聴き、わかったことがある。それは、首里城がまさに沖縄の歴史や文化の象徴であること。したがって首里城は沖縄の「誇り」であること。そして「誇り」が火災でも失われていないことだ。かならずや首里城は再復元されるだろう。所有権が誰であれ、財源がどうであれ、あくまでも沖縄が主体となってやりとげるにちがいない。
15世紀から19世紀まで約450年間、東シナ海に独立国としての琉球国が存在した。琉球国は「平和と守礼の国」であり、中国、朝鮮、日本などアジア各国との交易で栄え、多様性あふれる独自の文化を築きあげた。世界をつなぐ架け橋の役割をになうことで国を立てたのだ。したがって王城たる首里城は、軍事施設というより外交・交易・文化交流の拠点であり、まさに琉球文化の象徴である。
中国への冊封の時代があり、薩摩藩から制せられ、琉球処分では沖縄県となり、そして沖縄戦の凄惨をきわめた沖縄。戦後はアメリカの施政下におかれ、1972年に日本復帰、そして今、基地問題で大きく揺れている。今年2月の県民投票で沖縄県民の意思が明確に示されたが、政府はこれに応えられずにいる。そこにきての首里城焼失なのである。
わたしは、沖縄の基地問題が、「負担の軽減」といったレベルで解決できるとは思ってはいない。冷戦終結後のドイツが、在独米軍基地を縮小させ、地位協定を改訂して主権回復をめざしたように、敗戦国日本がみずから解決しなければならない国家主権の問題だと考えている。「主権はどうあれ米軍に守ってもらいたい」「基地はそのまま沖縄で引き受けてほしい」といった思考のままで、日本の独立が守れるとは全く思わない。
沖縄県民は、首里城を失ったことで、あらためて「誇り」を自覚したようにみえる。きっと、琉球国以来のアイデンティティを再認識されたのではないだろうか。この際、わたしたち日本国民みんな、琉球国の生き方に思いを致してみることが大事ではないか。そしてそれが、基地問題の本質を考える機会になることを願う。「日本に復帰してほんとうに良かった」と心から感じてもらえる日本であるために。
北東アジアに集団安全保障メカニズムを
2019.10.28
孫文は、1924年のいわゆる大アジア主義演説のなかで、『今後日本が世界の文化に対して、西洋覇道の番犬となるか、あるいは東洋王道の干城となるかは、日本国民の慎重に考慮すべきことである』と説いた。しかし日本は聴く耳を持たず、結局のところ、世界で孤立し、破滅した。今あらためて考えてみると、孫文の言葉は、『西洋覇道』を突っ走る当時の日本への痛烈な非難であったと同時に、今日の覇権主義中国への鋭い警告のようでもある。
戦後の日本は「平和国家」を標榜し、軍事力ではなく法律や規則、外交交渉や国際協調をむねとして生きて来た。自由貿易の恩恵を受けて経済発展をなしとげ、国際貢献にも尽力して評価を得ている。わずか一世紀あまりの間に『西洋覇道』と『東洋王道』の双方を、身をもって経験した日本は、「覇権主義による繁栄は長続きしない」「平和と安定こそが各国の国益である」という教訓を、いまこそ確信をもって語るべきだろう。
北京で開催された「第15回東京・北京フォーラム」に参加した。日本と中国がお互いに遠慮なく本音をぶつけあう姿は、少々意外だったが新鮮でもあった。パネルディスカッションでは、「日中はどんな協力をすべきか?」との問いに応えて、いくつかの提案をした。
まず、「北東アジアにおける集団安全保障の枠組みづくり」である。フォーラム全体の雰囲気や日中共同世論調査をみると、ぼんやりとだがコンセンサスができつつあるように思う。決して容易なこととは思わないが、是非とも米中を巻き込んで実現したい。その意気込みを、今のうちから、高らかに宣言しておかねばならない。
次に、その枠組みづくりへのアプローチとして、「透明性の向上」を提案した。疑心暗鬼を生ずるのは、見えないから疑念が膨らむのだ。透明性が確保されれば相互理解、相互信頼へとつながるだろう。この透明性の原則とは、第二次大戦後の欧州で、情報交換、相互通知、検証などを通じて軍事行動を抑制しようと提唱されたもので、現在も、核軍備・軍縮を実施するうえで、透明性・不可逆性・検証可能性の三原則のひとつとして有効に機能している。まず日中が、軍事面での透明性を向上させることが第一歩となると思うのだ。
さらにもう一つ。千里の道も一歩から、なのでまず手はじめに、「北朝鮮の非核化」での協力を呼びかけた。唯一の被爆国日本と、北朝鮮と近い中国が、ともにリーダーシップを発揮しましょう。アメリカを、韓国を、北朝鮮を、モンゴルを、そしてロシアを説得して、七か国による会議を常設しましょう、と。
欧州連合(EU)は仲良しクラブとして生まれたのではない。戦争回避のための知恵と努力の精華なのである。世界情勢が流動化しはじめた今、まずは北東アジアに、何らかのかたちで集団安全保障の枠組みを創りあげたい。多国間協議による戦争回避のメカニズムが欲しい。たとえ時間がかかろうとも。
帝国主義の時代から今日に至るまで、アジアは分断されたままだ。世界の平和と安定のために、今度こそ『西洋覇道』ではなく『東洋王道』をもってアジア諸国と協調していく。それが、日本の天命であろう。
海自艦派遣に反対する
2019.10.20
政府は18日、「中東地域の平和と安定、我が国に関係する船舶の安全確保のために、独自の取り組みを行っていく」(菅官房長官)と表明した。いわゆる有志連合に直接には参加しないものの、海上自衛隊部隊を中東に派遣し、得られた情報を米国に提供するなど、「米国とは緊密に連携していく」(同氏)とした。米国の意向に配慮するがイランとの関係も悪くしたくない、どちらにもいい顔をしたいとの意図がすけてみえる。詳細はあきらかではないが、少なくとも上記の趣旨であるかぎり、断乎として反対である。
まず、派遣の理由がない。そもそも自衛隊は、日本国と日本国民を守るために存在する。その海上自衛艦がいったい何のために中東海域を遊弋するのか。いったい何を「調査・研究」(防衛省設置法)するのか。漠然と「中東地域の平和と安定」のためと言うだけでは理由にならない。憲法はこのような自衛隊派遣を政府に許してはいない。
「我が国に関係する船舶の安全確保のため」というのも取って付けた物言いである。現状、中東海域に日本船舶への明白な危険は生じていない。つまり、自衛艦派遣の正当な理由はどこにも無いのである。
私たちは、今一度、歴史を顧みるべきだ。日本は近代化以降、対外問題解決に軍事力をもって臨み、結果として国を滅ぼした経験をもつ。その反省に立って、戦後日本は「他国の紛争に軍事力をもって介入しない」ことを国是とし、法律と規則、交渉や協調をもって外交を展開してきたのである。例外的に自衛隊を派遣する場合には、少なくとも、国連安保理決議や特別立法など、明確な大義と根拠を掲げ、国会の論戦・議決を経るのをつねとしてきた。今回、手続きも、差し迫った危険も、明白な理由もなく、なしくずしに自衛艦を出すならば、それは、戦後日本の外交方針を根幹から変更することになる。いったい誰が、いかなる責任において変更するというのか。
第二に、日本外交にとってダメージが大きい。この六月、米国イラン双方から請われ安倍首相がテヘランに赴いたように、日本はこれまで、日本でなければできない役回りを引き受けて、非軍事的な手法で紛争解決に努力してきた。難しい場面で大切な役割を担ってきたのだ。しかし、ここで自衛艦を派遣してしまえば、もはや調整役たりえずこれまでの努力は台無しとなる。日本の説得力・調整力も失われるだろう。
そもそも発想がいかにも姑息である。米国、イラン双方に気をつかい、うまい“おとしどころ”を見つけたつもりで自己満足している図である。日本人同士の内輪ならともかく、国際社会で通用するとは思えない。米国の側に立って地域介入する以上、イラン側からは敵性行動とみなされよう。そして結局のところ、国際社会の眼に映るのは“意思をもたないニッポン”“米国に付き随うだけのニッポン”という姿である。サムライの国がそんな不名誉にあまんじてよいものだろうか。
第三に、この地域の紛争には、つねに、キリスト教とイスラム教の対立が直接的あるいは潜在的にかかわっていると言われる。日本はそのどちらにも敵対しない、宗教的寛容さをもつ文明圏であり、ここにこそ日本外交のアドバンテージがある。それを、いとも簡単に投げ捨てて、米国十字軍の一員となって良いはずがない。日本を、千数百年にわたる宗教間抗争に巻き込ませてはならない。
旧オスマン帝国が欧州列強によって分割され、それから百年のときをへて、イランやトルコが台頭してきた。いま、中東で起きているのは、ダイナミックな世界史レベルのうねりである。シリア・トルコの対立、クルド民族、様々な問題に米国やロシアも複雑にからみ合い、どこからどこへ飛び火するのかわからない。「中東地域の平和と安定」などと軽々に自衛隊を出して、取り返しのつかぬことになるのを恐れる。
防災の体制づくりが急務
2019.10.16
台風19号は甚大な被害をもたらしました。亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げ、被災各地の皆様にお見舞いを申し上げます。一日も早く復旧復興を果たし、日常生活を取り戻されることを切にお祈りしたします。
温暖化の影響だろうか、近年の風水害はあきらかに頻発化、激甚化している。加えて、都市化や各インフラの稠密化もあるのだろう、われらが国土は災害に対し、より脆弱になっているように思えてならない。津波後の原発事故、地震後のブラックアウト、台風後の長期停電の例にみるとおり、ひとつの自然災害がその後、二次的あるいは複合的に拡大して、国民生活に複雑な被害をもたらす。経済や産業活動を妨げ、あるいは首都機能を脅かし、ひいては国家存続まで危うくすることもありえないことではない。
現在、内閣府には防災部門がある。災害のたびごとに職員諸氏の献身的な働きぶりに頭の下がる思いがしている。しかし、災害の態様がここまで広範囲、複層的、大規模になり、現代社会に乗数的にダメージを与えるようになったことを考えると、ここで思い切って、国をあげての防災体制を整えるべきではないか。日本列島のみならず世界中の事例研究を含め、あらゆる災害への備えについて考え抜き、一年三百六十五日、来る日も、来る日も、あらゆる事態を想定した対処準備、防災技術の研究開発、防災教育・訓練などを担う。そんな体制づくりが必要ではないか。ここに人員も予算も集めるべきではないか。
「防災省」創設は、今日いよいよ一段の説得力をもつに至った。日本がその気になれば、次から次に発生する災害から国家国民を守りぬくのはもちろんのこと、ハード・ソフトあらゆる分野でイノヴェーションを誘発し、それが世界人類に貢献し、ひいては日本を新技術立国へと導くだろう。
消費税、増税に思う
2019.10.8
なぜ財政がここまで悪化したのか。この三十年を振り返れば、理由は一目瞭然となる。実は、この間、公共事業費も、教育関係費も、防衛費も増えてはいない。増えたのは、社会保障関係費とこれに伴う公債費のみ、であった。増加分はすべて借金で賄われたかっこうで、借金が積もりに積もって、ついに国が立ちゆくかどうかというところまで来た、というのが真相だ。要するに、財政問題イコール社会保障問題なのだ。
日本の社会保障は、よく「中福祉・低負担」と表現される。国民は「負担」以上の「給付」を享受しているわけで、これが続く限り、財政赤字はふくらみ続ける。世間には、極端な楽観論もあるようだが、この世に「打出の小槌」など存在しない。身の丈以上の生活を続ければ、いずれ破産するのは当たり前のことだ。
財政と社会保障を持続可能にするには、国民の「負担」と「給付」をバランスさせるしかない。改革には大きな「痛み」がともなう以上、いかにして国民に理解を求めるか。いかにして国民の協力を得るか。ここが、日本の分かれ道になる。
十月一日、一部商品を除いて消費税率が10%に引き上げられた。これまでに二回の延期、そして軽減税率導入、あるいは使途変更と、右往左往した末の、ようやくの10%である。さらに増税にあたっては、様々な痛税感の緩和策や景気対策が用意されたが、かえって複雑で分りにくいとの指摘もある。選挙民との対話でしばしば耳にするのも、「バラまくのなら、そもそも増税は不要ではないか」という困惑の声である。「社会保障を守るための消費増税」という一番肝心なメッセージが届いていないのだ。国民の理解と協力なしには成しとげられない大問題なのに、その目的すら伝わっていない。われわれ政治に携わる者は、ここを、痛切に反省せねばならない。たとえ国民に不人気な政策であろうと、まっすぐ国民に語りかける率直さ。いま、国政に一番必要なのは、この率直さ、愚直さではないか。
野田内閣当時、与党たる民主党と野党の自民党・公明党とで、「税と社会保障の一体改革」を合意した。8%、10%の消費増税はここで決めたものだ。先進国で、これほどの増税を与野党協力して合意した例は他にみあたらない。与野党対立をのりこえた点、わが議会民主制の成熟度を示すものとして、もっと評価されてよいと思う。
残念ながら、当時の信頼関係は、今はすでに崩れてしまったかに見える。しかし、もう一度、与野党が協力して、次なる「税と社会保障の一体改革」に着手すべきだ。10%が実現された今こそ、時をおかずに、今後の道すじを示すべきである。
何のための憲法改正か
2019.9.26
憲法改正の議論を活発化させたい自民党だが、なかなか気運が高まらない。そのせいか、苛立ちの声もちらほら聴こえてくるのだが、問題はわれら自民党の側にこそあると感じている。
憲法は国民みんなのものだ。憲法を改正すると言うのなら、「日本国と日本国民のために、どこを、どう変えるのか」を徹底して考え抜かなければならぬ。「ああ、なるほど」と国民の納得と共感を得られる議論でなければならぬ。私の見るところ、今回、そのプロセスを踏んでいるとは言えない。今からでも、しっかりと考えることだ。その上で、大事業を行う覚悟をもって国民と向き合うことが肝心ではないか。
ひとくちに憲法9条と言うが、9条は第1項と第2項からなる。第1項は、いわゆる戦争放棄、平和主義を謳っており、変えるべきでない。ここに異論はないだろう。問題は、第2項だ。なかでも「国の交戦権はこれを認めない」との条文が、交戦権すなわち自衛権もないと解釈されうることが問題である。わが国に攻め込んできた外国を迎え撃つことすらできない、とも読めるような条文であることが問題なのだ。なぜ、こんな奇怪な書きぶりになっているのか。その問いに対する答えはシンプルだ。憲法制定当時、わが国に主権が無かったから。主権が無いから交戦権も無い、ということだ。その後、主権回復したから9条2項も削除すべし、ということで憲法改正が自民結党以来の党是とされてきたのである。
ところが、安倍総裁が唐突に「9条2項は削除しなくていい。『自衛隊』と書き加えればそれでいい。」と言い出して、いつのまにか自民党案のごとく扱われるようになった。仮に、である。仮に、安倍案でいくとするならば、たしかに自衛隊は合憲となるだろう。しかし、そもそも日本に自衛権があるのかどうかの根本問題は、曖昧なまま残ってしまう。憲法のどこが問題なのか、どうすれば解決できるのか、きちんと考え抜いた改憲論議をすべきではないか。
ところで、この9条2項の議論とは別に、自衛隊と憲法の関係を整理する上で、重要かつ喫緊の論点がある。それは、国連平和維持活動(PKO)に関することだ。(※PKOに基づき派遣される軍隊をPKFというが、以下では煩雑になるのでPKOで統一する。)
かつての国連PKOは、紛争が落ち着いた状況下で行うものとされたが、今はそうではない。ルワンダ虐殺を傍観した反省からアナン事務総長のときに、国連自身が紛争当事者になる決断をし、国際人道法(以前の戦時国際法)を遵守する決定をした。つまり、PKO部隊自身も武力紛争の当事者となりうることになり、その結果、自衛隊のPKO参加に、憲法との矛盾が生じてしまったのだ。派遣される自衛官の法的身分もまた、曖昧で不安定なものとなった。したがって、ここをきちんと整理しなければならない。
どうすべきか。選択肢は二つだ。一つは、憲法と矛盾するから国連PKOには参加しない、とする道。もう一つは、憲法との矛盾を整理して、紛争当事者となることを前提に、国連PKOに参加する道だ。日本が国際社会で生きていくために、どちらの道を選ぶべきだろうか。私は、後者だと考えている。
わが国が、こうした国連PKOに参加するためには、自衛隊が国際人道法を遵守すること、国際人道法が求める法的環境を整え、自衛隊そして自衛官の法的身分をハッキリさせておくことが必要だ。ズバリ、戦争犯罪に関する軍法と軍事法廷が必要なのだ。そして、これは憲法76条の改正をも必要とする。自衛隊と憲法の関係をきちんと整理するための、重要かつ喫緊の論点はまさにここである。
南スーダン撤退以降、わが国はPKOに部隊を派遣していないが、今後、法的環境を整備せぬままPKOに参加すべきではない。自衛隊・自衛官を、国際法上の正当な身分が与えられぬまま海外派遣してはならない。この際、自衛隊と憲法との関係を整理し、必要な法体系を整えた上で、国連PKOにきちんとした体制で臨むべきである。
このように、憲法改正とくに9条の議論をするならば、「どうすれば、国家の独立と国民生活の安寧を守れるか」「どうすれば、国のために体を張ってくれる自衛官を正しく処遇できるか」ということを、とことん考え抜かなければならない。それは、政治の責任である。
[追記]:本稿執筆中の25日、安倍首相は、国連総会において「2022年国連安保理・非常任理事国への立候補」を表明した。国際人道法に適応する法体系を持たないわが国は、理論上、国連PKOに参加できない状況にある。憲法の本質的課題に向き合わぬまま、一足飛びに「非常任理事国」に名乗りをあげたかっこうだ。しかしこれは、国際社会に対する誠実な態度といえるのだろうか。
断じて、「有志連合」に参加してはならぬ
2019.8.24
ホルムズ海峡の航行に不安があるというので、米国がいわゆる有志連合による船舶護衛を呼びかけている。すでに、英国とバーレーンにつづきオーストラリアも参加を表明した。日本も参加を働きかけられているが、「総合的に検討する」(岩屋防衛相)のコメントにみられるとおり、日本はこの件につき明確な判断を示していない。はたして日本は、「有志連合」に参加して自衛隊を派遣すべきであろうか。これに関して私の考えは明快である。断じて、この「有志連合」に参加してはならない。
わが国は、近代化以降、軍事力をもって海外に展開し、結果として国を滅ぼした経験をもつ。その反省に立ち、戦後の新日本建設にあたっては「他国の国際紛争に軍事力で介入しない」ことを国是として固く誓ったのである。平和創造のためには、国連決議を目印に汗をかくことにやぶさかではないが、外交がままならぬから軍を出すなどという道とは訣別したのである。これまで我が国は、法律と規則、国際交渉と国際協調をもってやって来たし、その足跡は国際社会から一定の評価を得られているものと自負してよい。
そこで今回の件であるが、まず、日本の国華産業運行のタンカーが攻撃された事案は、いったい誰が、何のために攻撃したのか、真相はいまだ、まったくもって「藪の中」である。その後も、日本の船舶が攻撃を受けたり、拿捕されたりする事案は一件も発生していない。したがって、少なくともわが国にとって明確な脅威がホルムズに発生しているとは言えない。さらに六月に、わが国の安倍首相が米国から請われ、イランからも請われてテヘランに赴き、両国の間に立って仲介・周旋の努力をしている途上である。難しい調整役を引き受けて、そこに全力を注ぐ姿を見せることは、国際社会からの信頼をかちとる上でどれほど重要なことか、言うまでもないだろう。ここで自衛隊を出したのでは調整役たりえなくなるのである。戦後日本の外交理念に照らしみたとき、「有志連合」には一ミリの迷いもなく「不参加」を表明すべきである。
一方で、「米国の意向を無視できるのか」「多少問題あっても米国に従うべきだ」という声もあるだろう。しかし私は、米国追随のメンタリティーで自国の安全保障に関する意思決定をしてはならない、ということをことさらに強調したいと思う。そもそも米国追随路線は、この先行き止まりの袋小路になっている可能性が高いからである。
私がそう考えるには理由がある。第一に、米国は自国の利益を減じてまで、日本防衛にあたることはないという現実だ。それは、尖閣諸島の領有権に関し中立の立場をとっていることや、いわゆる「核の傘」が〝あって無きが如きもの〟であることからしても明白である。
第二に、米国の国際戦略はどう見てもうまくいっているようには思えない。国連の賛同が得られなくとも有志連合を組織して軍事力行使に踏み切る、というやり方が、はたして有効だったのかどうか。アフガニスタン戦争や、イラク戦争をみれば明らかではないだろうか。軍事力行使をためらわない米国流は、何より米国自身を疲弊させるし、世界の安定確保という意味からも疑問ありと言わざるをえないのである。
第三に、日本の独立を担保するのは、「自国は自国で守る」という、我ら自身の自主自立の気概である。しかし、米国追随のメンタリティーは、これを真っ向から棄損している。
激動の世界の中で、米国であれ、どこであれ、その国益に反してまで日本を守ってくれる国など存在しない。日本が独立国家だと言うのなら、苦しくとも、のたうちまわりながらでも、自主自立の気概を拠り所にして、国際社会の中で生きていくしかないのである。
イランに対しても、言うべきは言わなければならない。世界唯一の被爆国として、核兵器に対して厳しい姿勢を示すことは、日本の天命ともいうべき役割であろう。北朝鮮の核開発は声高に非難するがそれ以外は無関心ということになれば、自分の利益にしか興味がない国とみなされて、我が国の主張に説得力は生まれない。世界の平和と安定のために、諄々と理想を説く資格が日本にはあるのだ。核兵器を否とする確固たる理念を表明し、核不拡散の国際ルールづくりに取り組むことこそが、日本外交の存在感を高め、日本の安全保障にとって大きな力になると信じる。
いわゆる有志連合に安易にのってしまうことへの私の最大の懸念は、千年にわたるキリスト対イスラムの抗争に、我が国が巻き込まれることにある。米国がイラン核合意から一方的に離脱して独自の制裁を言い始めたことから、今回の緊張状態が生まれた。しかし、この対立は、何らかの経緯で宗教間抗争に飛び火しないとも限らない。実際、現下の国際社会には、キリスト対イスラムの不協和音が通奏低音のように流れているではないか。
日本は外交下手などと言われながらも、こと中東においては独特の中立的な立場を有している。日本が、キリスト教国でもなく、イスラム教国でもなく、また「八百万の神々」というように、多様な文化・宗教に寛容であることも理由の一つであろう。とくに日本とイランとの間には、出光の石油買付けやアザデガン油田など、「義侠心」をともなう特別な交誼があるではないか。
そんな日本を、千年抗争に巻き込ませてはならない。それは、もちろん日本のため、かわいい子や孫のためであるが、同時に世界のため、人類の未来のためでもある。世界の中に、宗教的寛容さをもち、対立や競争よりも調和と共生を説く文明国が、ひとつくらいなければならない。私は、そのように思うのである。